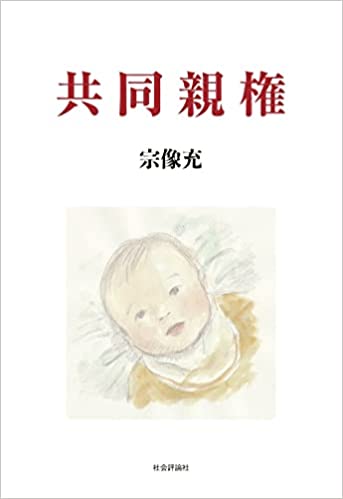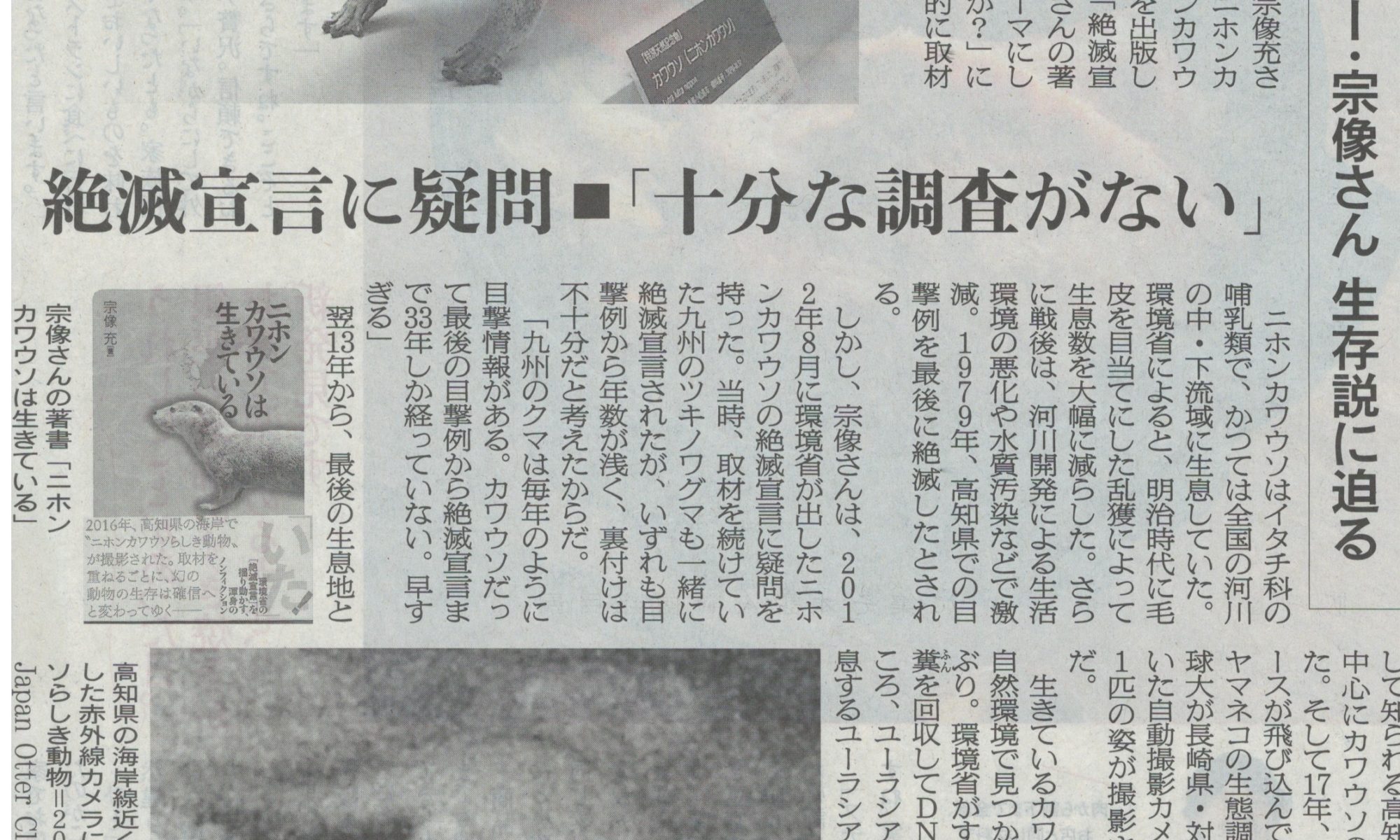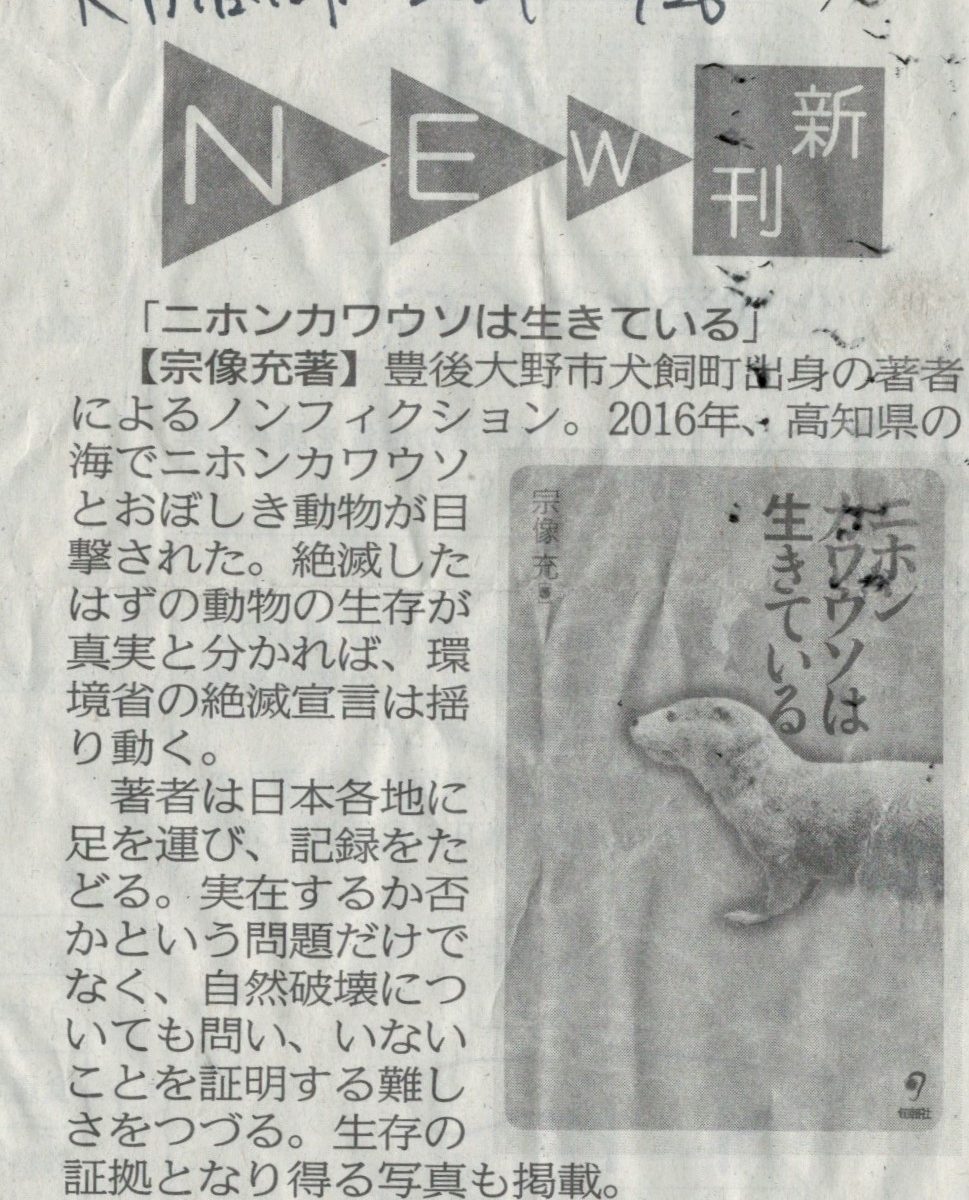読者を愚弄
12月5日に沖縄県の地方紙、沖縄タイムスは、憲法学者の木村草太の連載コラム【木村草太の憲法の新手】(165)で「離婚と親権(上)『連れ去り勝ち』論に誤り 報道は双方の取材必要」との記事を掲載し、ネットで配信して読めるようになっている。
木村氏は現在の実子誘拐や単独親権制度についての報道記事について危惧があり、報道の問題点を挙げるという点でコラムを書いている。
例えば、「連れ去り勝ち論」について木村氏は、不当な子連れ別居に対しては、監護者指定や子の引き渡し手続きがあり、虐待親であれば監護者として不適切な親から裁判所が引き渡しを命じるなどと述べ、面会交流の手続きも保障されているので、「連れ去り」が主張された事例では、報道機関やライターは、別居親に、裁判所で監護者指定や面会交流の手続きをとったかを確認すべきだという。そうしないとDVや虐待の加害者に加担する危険があるし、監護者指定審判の中で、深刻なDVや虐待が認定されているのに、それを無視して、「実子誘拐の被害者」などと報じれば、子連れ別居を選択せざるを得なかった親への深刻な名誉毀損となるというのがその主張だ。
子連れ別居を選択せざるを得ない状況は現行制度の不備だと思うし、そういう点では、双方が制度の被害者だと踏まえた上で一応述べておくと、別居親の中で子連れ別居から子の引き渡しや監護者指定で勝ったという事例はまず聞かない。あるとしたら、子どもが生死不明に陥る程度の深刻な虐待でなければ家裁は虐待など認定しない。子どもが多少の怪我をする程度の虐待や、現在ではモラハラや精神的虐待と言われる程度の虐待の加害者が同居親である事例は、別居親の話を聞いている限りにおいてはありふれている。
しかし裁判所はいくらそれを別居親が主張しようが、対立が強いとして間接交流という名の写真の送付や、月に1度2時間程度の面会を斡旋する。間接強制という強制執行を木村氏は肯定しているようだ。ぼくの事例では、間接強制によって子どもと再会できるようになるのに半年かかり、上の子との面会はそれ以来途絶えた。子どもが中学になれば強制執行はかからない運用を現在家裁は繰り返している。
木村氏がこういった家裁の実情を知らないとしたら「世間知らず」という批判はさておき、学者としては調査不足だ。知っていて言っているとしたら、自分の知名度の高さとメディアで連載を持てるという地位を利用した、別居親へのヘイトというしかない。要するに読者を馬鹿にしている。
木村氏は、おそらくこのテーマでコラムを書こうと思い立ったきっかけとなる、フランス人のヴァンサン・フィッショさんの妻に実子誘拐の逮捕状が出たことについて触れていない。フィッショさんは面会交流の調停手続きを避けているが、やれば子どもとの交流を制約されるわけだから、やらないのは妥当だ。子どもは誘拐の被害者だ。誘拐の被害者の子どもの写真など、報道機関が公開しないということはまずない。いちいち誘拐犯の言い分を聞かないと報道できないということもない。
要するに彼が狙っているのは、社会問題のもみ消しであり、口封じである。地位と権力のある彼だからできる「パワーコントロール」と呼んだらコントかもしれない。そして制度の被害者どうしの対立をあおり続け、彼はそれについて発言し続けることで地位を保てる。悪質である。
沖縄タイムス、やらかしたのは2度目
ところで、あまりにも現場の実情を知らない意見なので、編集部に電話したり、質問状を出したりしようと思ったけど、やめた。
すでに、沖縄タイムスは2018年に、木村氏の同連載コラムで、「(86)共同親権 親権の概念、正しく理解を 推進派の主張は不適切」、「(87)続・共同親権 父母の関係悪いと弊害大きい」と共同親権への木村氏の反対論を掲載していて、このときにもぼくは沖縄タイムスの担当編集者に直接電話し、その後質問状を提出しているからだ(http://kyodosinken.com/2018/10/04/oki nawataimusu/)。その後沖縄タイムスは、共同親権訴訟も含め、親権論議についてのシリーズ記事を掲載している(ネットでは一部しか見られない)。
「コラムの著者の意見。新聞社は載せただけ」という逃げは、今回の記事には通用しない。
このときの木村氏のコラムの中には、「裁判所は、別居親に監護の機会を与えてくれない」という批判に対し、それは、裁判所の人員や運用に問題があって、裁判所が適切な判断をできていないか、あるいは、客観的に見て別居親の監護が「子の利益」にならないことによる。法律の定めるルールの内容に問題があるわけではないと述べ、裁判所が人員不足も起因して適切な判断ができていないことを述べていた。
今回の木村氏の主張は、手続きさえ経ればきちんと判断されているということだから、前回の主張と食い違っている。要するに、別居親がまともじゃないというために、ときに裁判所は適切な判断をしている、ときに適切な判断ができないときもあると一貫性のない主張をその場しのぎでする。
ちなみに読売新聞は女性が94%で割合で裁判所で親権を得ることに対して、二人の元裁判官が、「裁判所には『子は母に』の考え方が浸透していた」、「本来はケースに応じて判断するべきだが、そうではなかった恐れはある」と述べ、裁判所の判断が性差に左右された恣意的なものであることを証言している。とすると、木村氏の主張は、裁判所のジェンダーバイアスを肯定する意図でなされたものであることがわかる。念のため述べれば、このようなヘイトが大手メディアで繰り返されれば、ますます男性の育児を困難にし、日本のジェンダーギャップ指数は低迷し続けるだろう。
以上指摘して、沖縄タイムスが求められているのは、今回の木村氏の記事に対してのファクトチェックを報道機関の責任としてなすことである。木村氏への反対意見を対抗言論や検証記事の形で紹介するべきだ。木村氏は、沖縄タイムスのコラムを利用しての、別居親や男性に対する「聖戦」を継続しており、それは今回のコラムでなされたような、ジェンダーバイアスを知悉した上での巧みな扇動ヘイト記事になることは目に見えている。沖縄タイムスは、木村氏の親権に関するコラムが物議をかもすことを知っていえ、ファクトチェックよりも掲載による話題作りを優先したのだから報道姿勢を問われても仕方ない。
読者のことを思うなら、こういう適当な意見をその場しのぎで言う憲法学者の起用をやめることである。(2021.12.7)