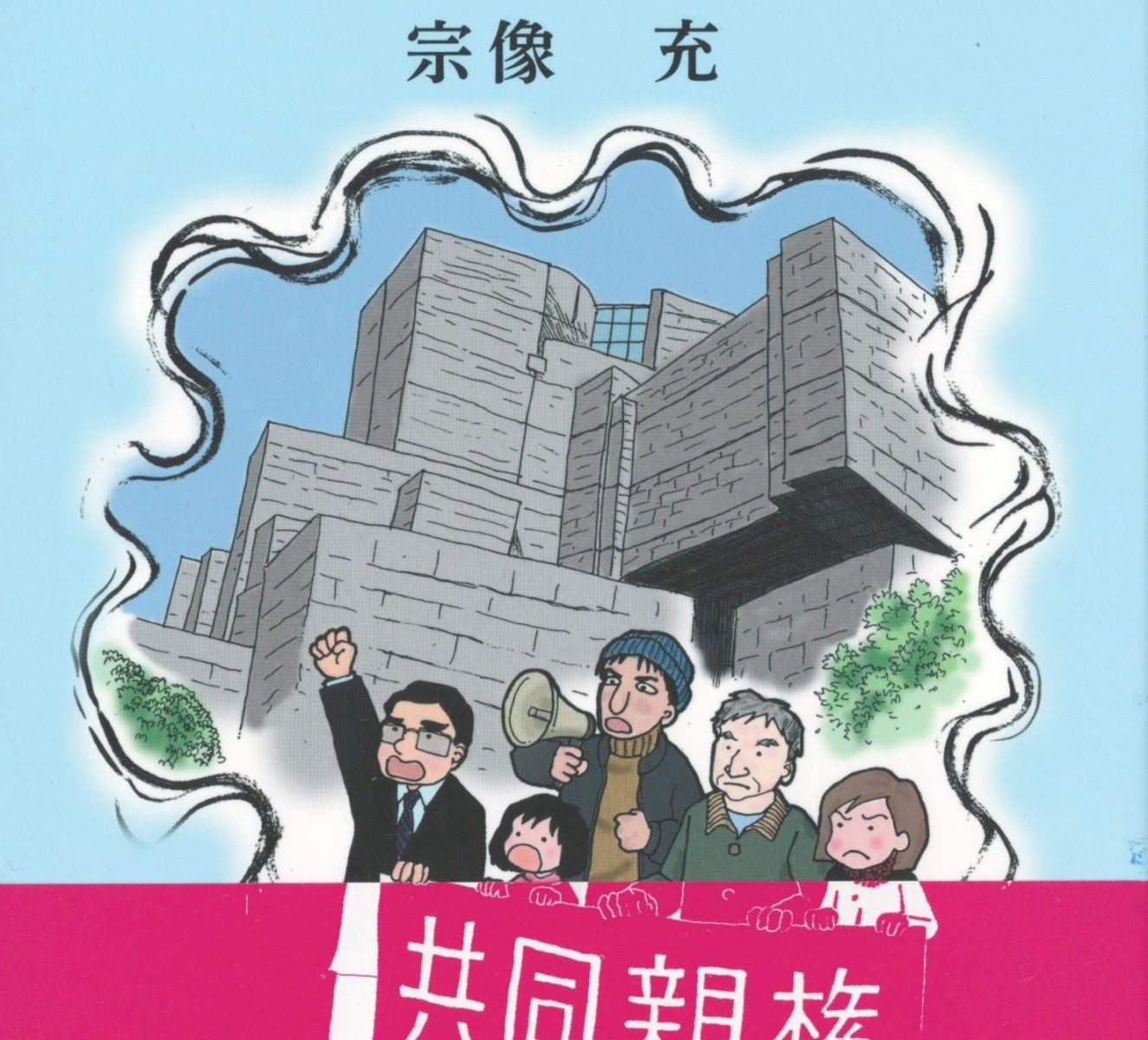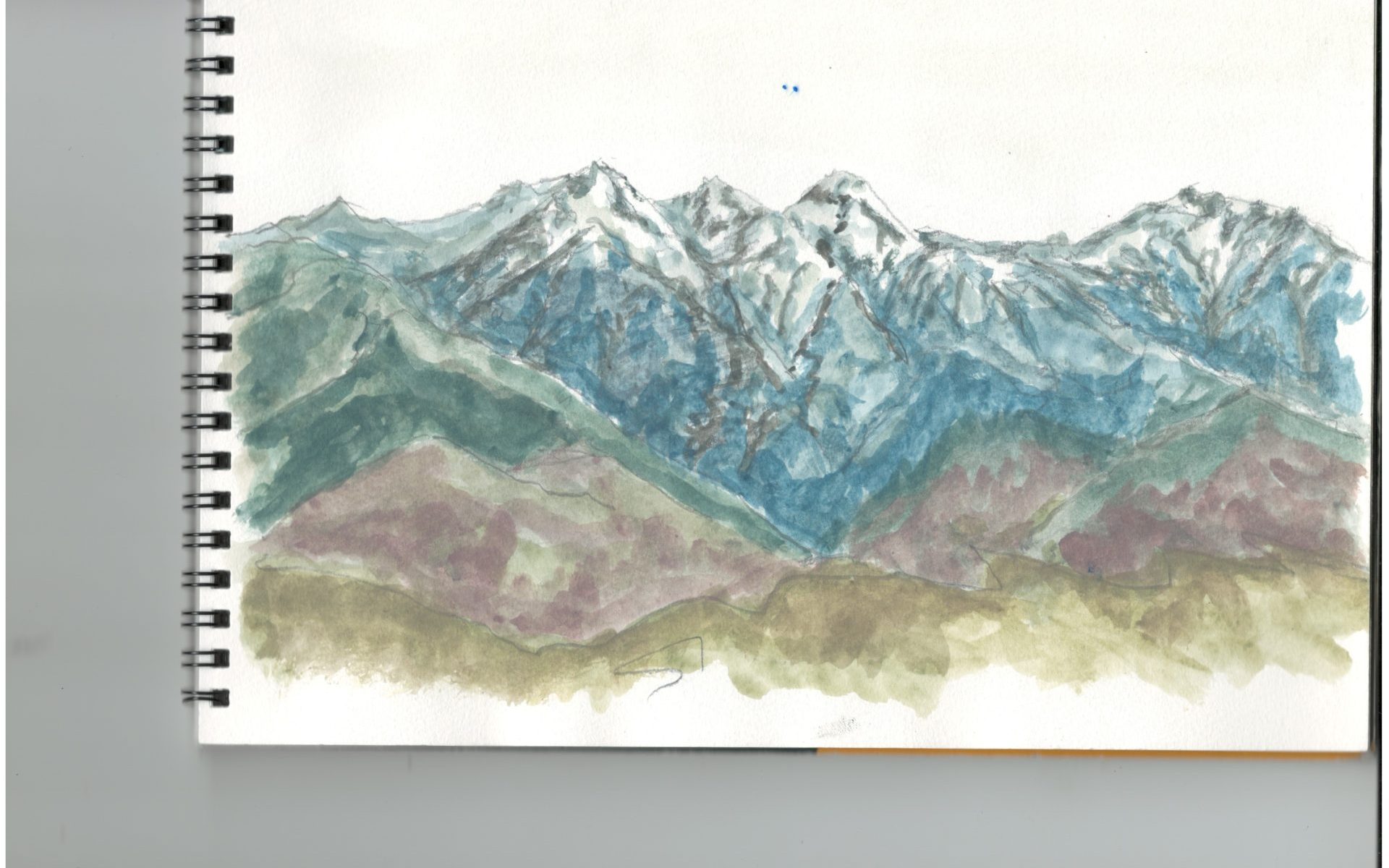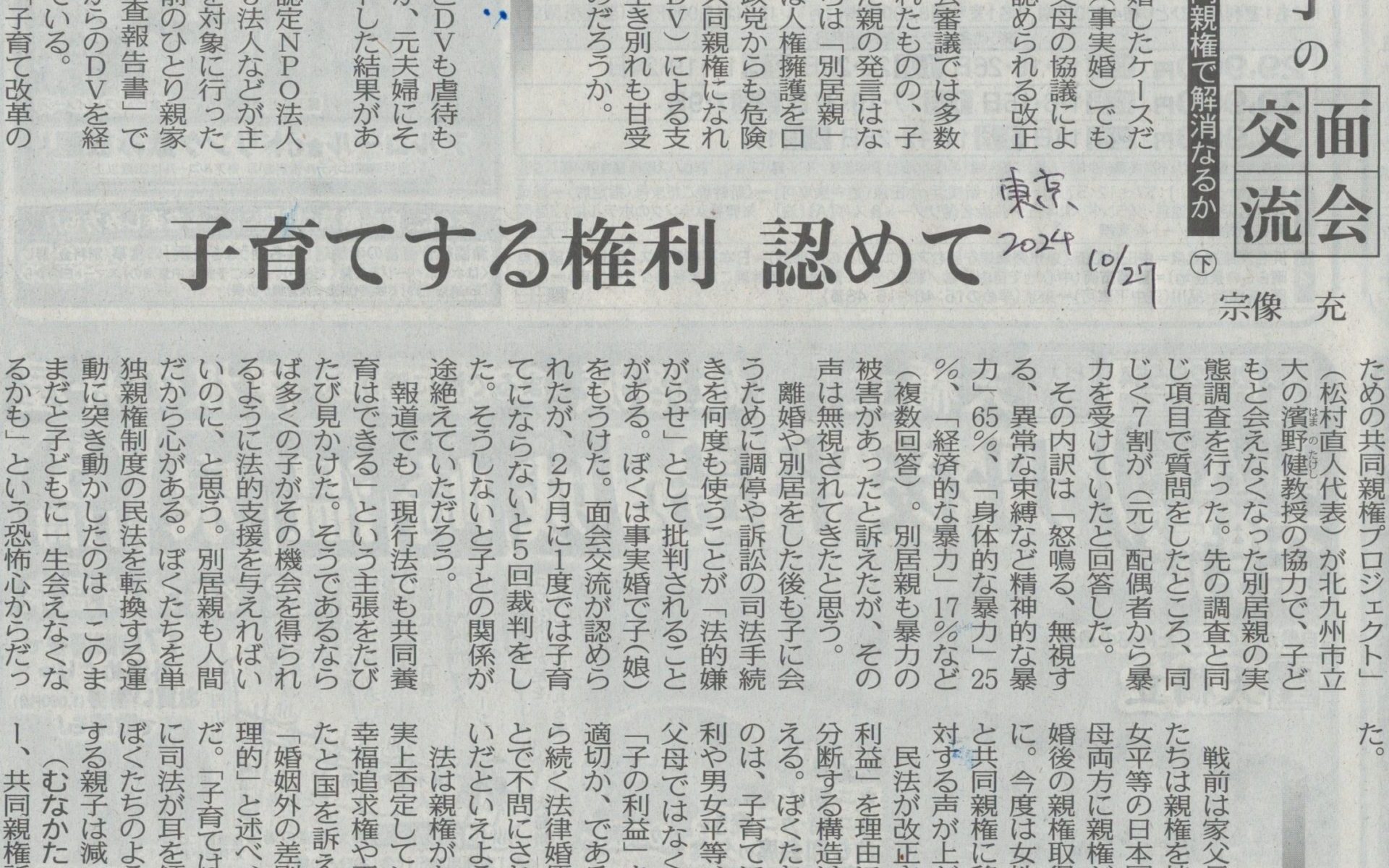「庭にフクジュソウがあるみたいで『ここにあるから踏むな』とか言うんですよね」
最近村内に越してきた山小屋仲間の椎名美恵さんがうちにやってきて、お茶を出すと村の驚き体験を披露してくれていた。
「私が家主なのに何でそんなの言われるんだって……」
近所の人たちのペースに合わせてたら、引っ越し作業はどんどんずれ込み、その上家主なのに自分ちの注意を受ける。
「ぼくも家で電話出てるときに上蔵(わぞ、この集落)の人がやってきて、『今電話出てます』とか返事したら『電話なんか切っちまえ』って言われたからね」
ギャハハと椎名さん。
「そういうの楽しめないと大鹿にはいれないんだなあ」
という彼女に「大鹿外国だからね」と説明したら肯いてた。最初から異文化なら「こんなはずでは」という程度も小さい。
ちなみにそのときぼくが玄関先に出ると、広報物を手渡され、うちの庭先の丸太を見てその人は「カラマツは腰掛けにはダメだ。とげが刺さる。カラマツはやめとけ」とひとしきり講釈を垂れ去っていった。
頼んでもないのに勝手に保護者になってお節介をお節介とも思わない。そこそこのところで「自分はそういうの無理なんで」と言えない人はたしかに苦労するだろう。
周囲に合わせて保護者たちの助言に従い、最終的には有力者の言うことを聞けば、それはそれでとりあえずは波風は立たない。だけども周囲に合わせるのに疲れて何のためここで暮らしてるんだ、と思う人が都会を離れて田舎暮らしをはじめるわけだから、そこはとりあえずもめごと必至なわけだ。
昨年4月から1年間、自治会長の役が回ってきた。上蔵には5つの班があって、順番にお世話班を回していて、お世話班が自治会長を出す。ぼくの暮らす峯垣外班ではさらに自治会長は中で順番で回しているから、20年か25年周期で自治会長は回ってくる。その1回目がうちにきた。
年に一度の村集会(上蔵の人は「村」と呼んでいる)の前の班長会で自治会の役を決める。班長会で決めればみんな従うのが以前のルールだったようで、ぼくも引っ越した一年目にいきなり役を告げられた。事前の依頼で決まらなかった役をその場で決めて集会で告げると、「聞いてない」「根回し不足だ」と大もめにもめて、まあ21世紀だしね、と思いはするけど、その間の調整に右往左往するのが自治会長の最初の仕事だった。
お世話班と自治会長の仕事はやってみると、役場の下請けの割り振りと、お祭り等のしきたりの段取り、がほとんどで、どんど焼きにしろお祭りにしろ、別にぼくがあれこれ指示しなくても村の人が勝手に動いてくれる。
ぼくが自治会長権限でやったのは、前年はまったく呼ばれなかった空き家対策の会議の様子が前任者からの引継ぎでは全然わからないので、村の担当者と決めて委員会として立ち上げたことと、コロナで途絶えていたお祭りの直会(神事後の宴会)がやるやらないでもめそうだったので、「やったほうがめんどくさくない」と実行したことぐらいだ。
ちなみに前年呼ばれなかった空き家対策の会議は有志でしていたけど、ぼくが呼ばない理由を「宗像さんはほかの人と仲良くしないから」とみんなの前で言われたことがある。自由だなあと思ったけど、次の会議で「自分のことをすぐに理解してもらおうとか思うてませんよ。そういうこと言われるとつらいわあ」と言いはした。
東京から越してくると、都会の人、ぐらいの印象は持たれるのだけど、実際はぼくは田舎育ちだ。親戚がいたとはいえ、父と母は農家ばかりの9軒の集落へのはじめての移住者だ。一升瓶を持っていったりとなにかれと周囲に気を使っているのを見ている。ぼくたち兄弟も、放し飼いのポチが隣の畑を荒らすと、「謝ってこい」と父の命令で隣のおばちゃんに頭を下げにいく、なんていう今考えると理不尽な体験もしてもいる。
ぼくがここで暮らし始めたとき、母は「部落んし(人)に歯向かうなよ」とありがたい助言を下さっている。父と母は今では長老格になっている。
退職してから自治会長をしていた父に大分に帰ったときに村のもめごとの話をしたら、笑いながら「上津尾(こうずお、実家の集落)でんみんな今も好きなこと言いよるわ。それでん部落っちゅうのはおもしりいよ。お父さんも若いころはいろいろ言うてみて、みんなが賛成せんかったら『早かったかな』とゆうて引き下がった。じゃあけんどだいたい昔言うたことは今そうなっちょるわ」という。そして「お前もみんなに信頼されるようにしよ」と言葉を足した。
何かと衝突してきた父子なのだけど、このときは多少うんざりもしていたので「どうしたらそうなるん」と素直に聞いた。「なるべく公平にしよ」と父は一言付け足した。
「お前んとこの親父が来ると法事が長くなる」と近所の人にはぼくたち兄弟は言われている。 「ただ酒飲んで長居して」と言われた父は、「借りは作らん」と次から自分の分の一升瓶は持っていくようにしたそうだ。それくらいで早めには切り上げたりしない。
村のリニア連絡協議会に自治会長だから呼ばれて、最初のときに「自治会に報告とかないわけだし、本来村の代表は村長と議員なんだから協議会やんなくてよくないですか」と発言してみた。すると「JRの説明はほしい」「出たくなければ来なければよい」との発言があり、これは任意の会議になる。村の担当者に「謝礼はいりません」というと、「それは困る」ということなので自治会に寄付した。
JRは本来であれば管理型処分場に持ち込むと環境アセスで言っていたヒ素入りの有害残土を、上蔵の川原の変電所施設の下部に埋め込むという。上蔵に事前に相談もなく村で説明会をしたJRの姿勢を4回にわたり「ぼくはきちんと説明を受けたとは思ってませんからね。当該自治会の自治会長として賛成したとはみなさないでくださいね」と念を押した。
道路の通行止めに関しては業者は自治会長の承認印をもらいにくるので、これで在任期間中は止められるかと思ったけど、実際は道路の通行止めはなかった。それでも期間中の工事をJRはせず、理由を聞いても答えなかった。
先日次のお世話班に集会場で引継ぎをした。明治時代から続く集会録も含め、昔はリヤカー一杯の引継ぎ物品を次の班へと持っていったという。今は石油ストーブの大きさぐらいの引継ぎ書類に、神社の蔵や福徳寺の鍵、余った一升瓶やらを渡す。
有害残土を置くことに、地区で反対決議を上げても業者には有効ではなさそうだ。行政は任意団体は小馬鹿にするけど、自治会の意向はなかなか無視できない。そこで、登山口につながる鳥倉林道のマイカー規制を、今日の集会の議題にかけるように、引継ぎでお願いした。地区の静かな環境維持のために一つぐらいは置き土産はしておこうと思った。
どんな意見が出るか、楽しみではある。(村集会ではそのまま了承されました)
(2025.3.24越路44 たらたらと読み切り184)