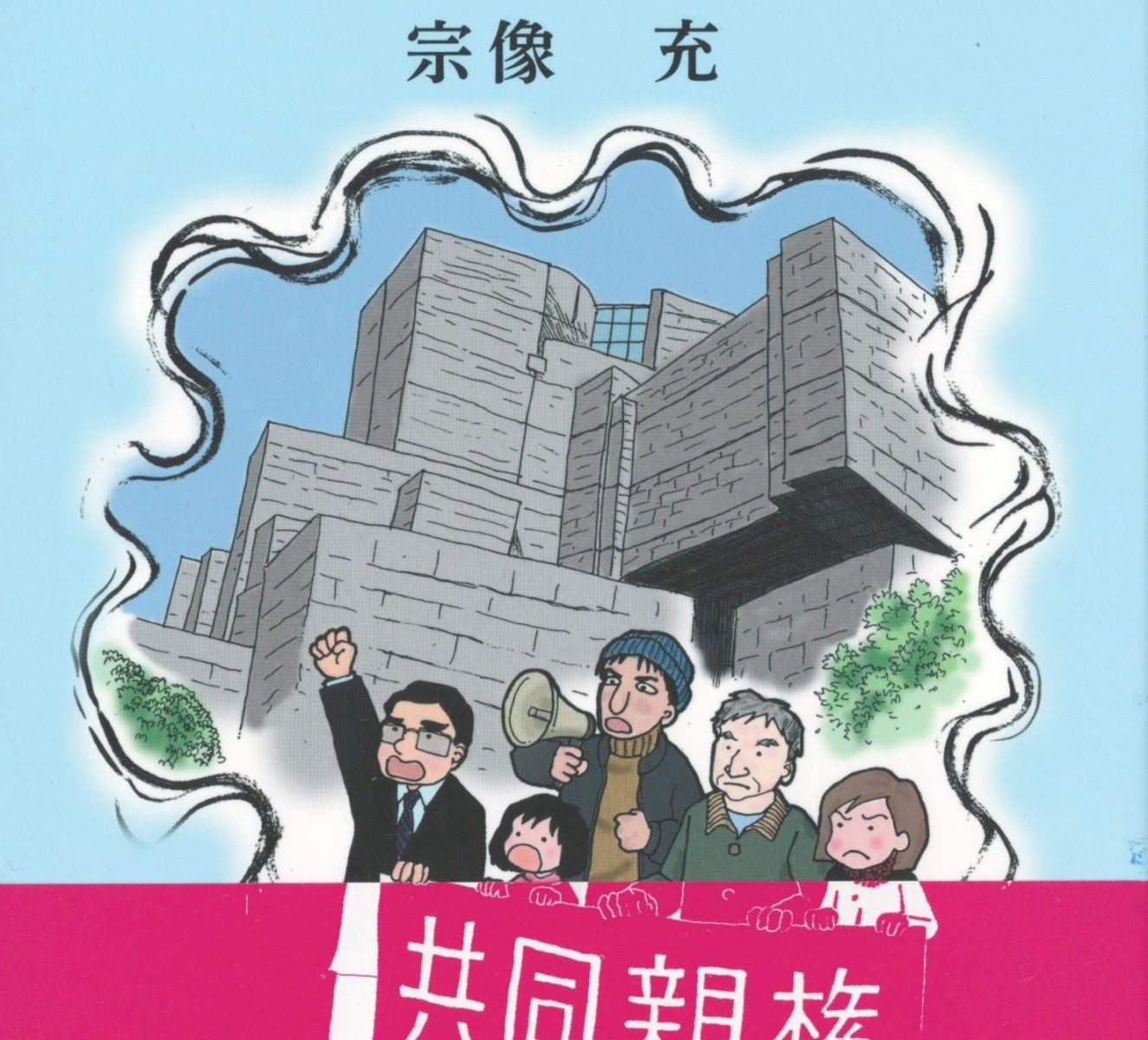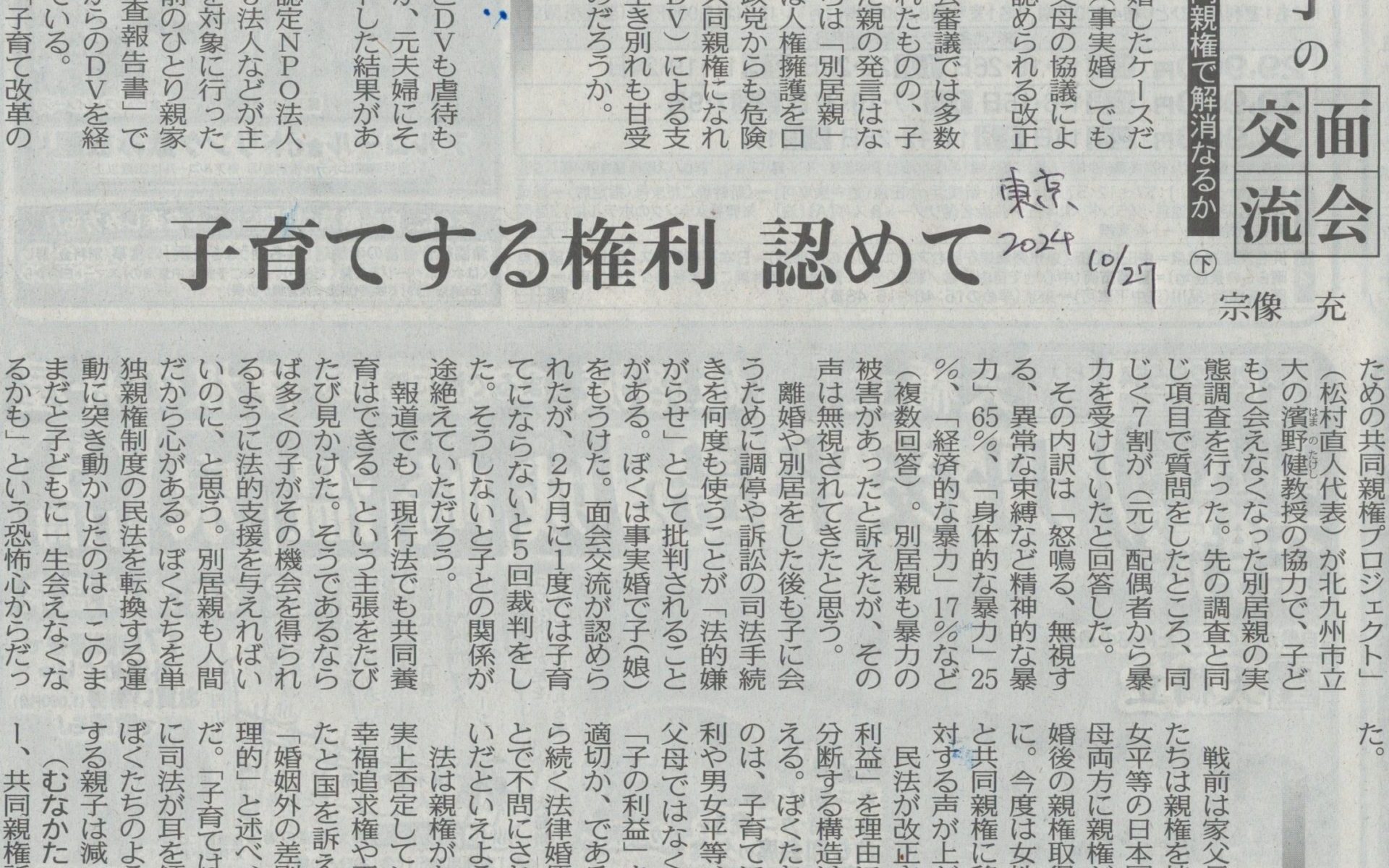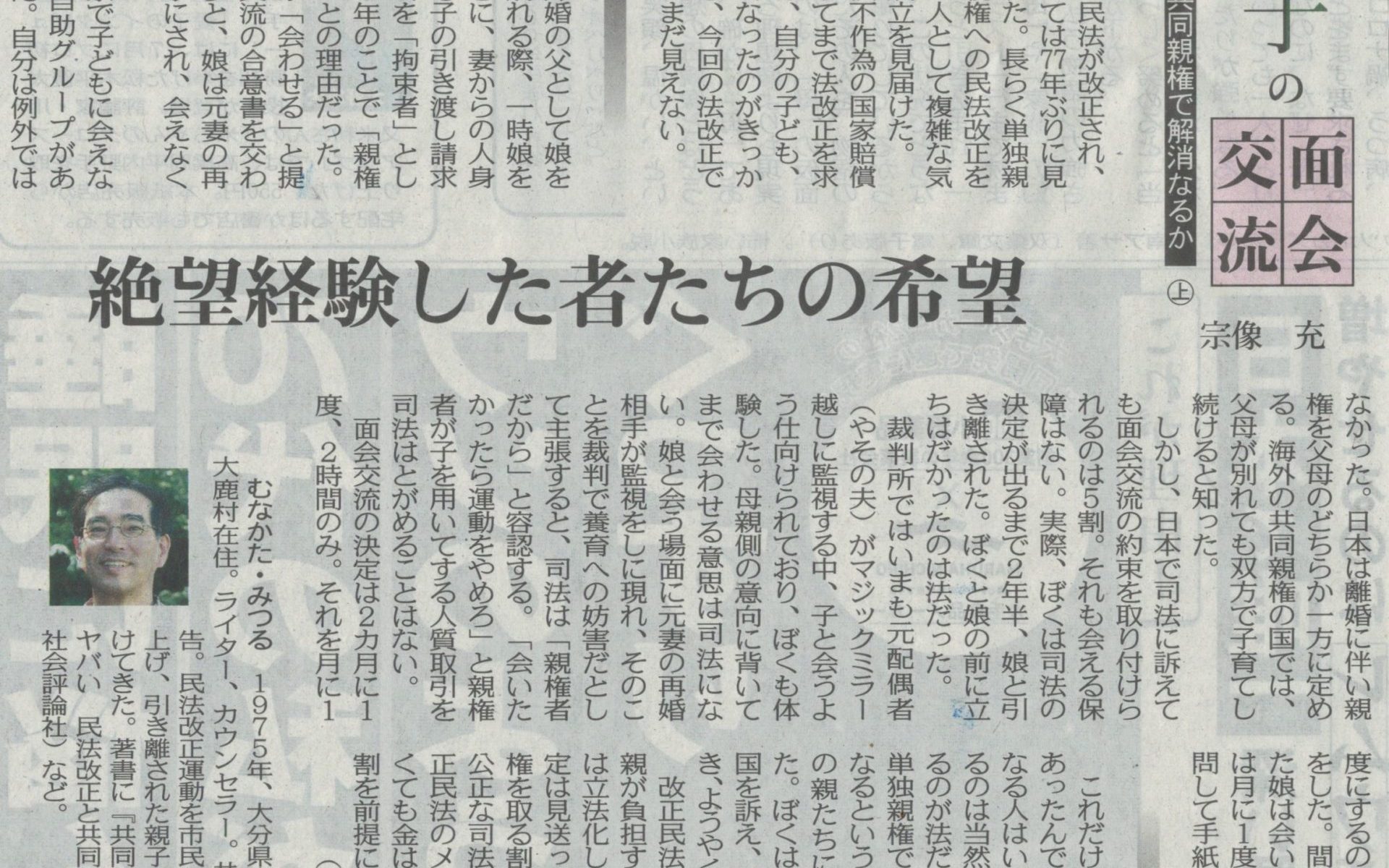「大鹿村にないものは、コンビニと信号と人権です」
連休に三伏峠小屋に手伝いで上がると、小屋番3年目で今年から大鹿村で暮らしはじめた椎名さんが、山小屋仲間にそう説明していた。
コンビニと人権がない地域はどこにでもあるけど、島でもないのに村に信号がないところはあまりない。信号なんかできたら切符切られる理由を警察に与えるだけだ。一番交通量の多い役場のそばの落合の交差点には一時停止の停止線もない。切符をやたら切りすぎる駐在は苦情が来て交代させられるみたいだ。ただ単に人口が少ないだけかもしれない。
夏シーズンに今年最初に山小屋に上がったのは7月の海の日の連休だった。このときはちょうど参議院議員選挙の最中で、連休中日が投票日だった。公選ハガキも来ないけど、ダム反対で現地で暮らす友達から、ほかにダムのことで質問してくれる人いないから嘉田由紀子に入れてくれ、とお願いされた。「維新かあ」と思いながらほかに入れたい候補もいなくて共同親権の件では知り合いだし、全国区は入れた。長野県区は世襲の立憲と同じ大学出の女性の元外交官。それに参政党とチーム未来だった。
秘境の選挙掲示板にも初日から参政党候補者のポスターが貼ってあった。勢いがある。一週間ほどしてチーム未来の候補者が貼りだした。どっちにしたって、中央政府の連中がこの辺で暮らす人に目配せする政治をするなんて想像できない。大鹿村に選挙カーが回ってきた記憶もない。考えるのめんどくさくて白票。
期日前投票を役場ですませて小屋に上がると、「投票用紙は来ません」と小屋番仲間たちから言われる。「投票用紙も投票箱もないんだね。刑務所でも投票できると思うよ」とぼくが言うと、「ここには人権ないんだあ」と相当ショックを受けていた。
歩荷さんも登ってきて、山小屋は連休中お客さんもスタッフも大人数で賑わった。それでも昨年の繁忙期のように、テント場にテントが収まりきらず、小屋の周りまで張ってもらうような事態にはならなかった。全員忙しく動き回って月曜日の海の日の朝は選挙も終わっていた。
イーロンマスクのおかげでスターリンクの山小屋WiFiはこの小屋にもある。朝の食事時に厨房でみんなでスマホ動画で選挙結果を見る。参政党の議席が二桁になっている。
「おれ言ってなかったけど実は参政党の党員なんだ」
同年配の歩荷さんがしゃべりはじめる。
「参政党の党員ってどうやったらなれるんですか」
とりあえず聞いてみる。
「ネットで1000円払うだけだよ」
すでに飯田下伊那地域で参政党の党員は数百人規模になっているという。共産党なんか凌駕している。後で調査結果を見ると、ユーチューブ動画の再生回数は長野県でも参政党が一番多かった。候補者もそこそこ票を獲得している。
「やっぱ神谷さんだよ。日本人ファーストだって」
半年前は「やっぱ国民民主だよ」って言ってた気がする。
「でも日本人だけで考えたらぼくたち多分ファーストにならないと思いますよ」
ぼくも歩荷と小屋番の手伝いをしにくるけど、世間的にはファーストだと思われていない仕事の地位向上が「日本人ファースト」で実現するとは思えない。
「それよか、ぼく『長野県民ファースト党』を作りました。入山料を都民から100万とりましょう。それで歩荷のキロ単価1000円にします」
40㎏上げたら4万円。
「党費いくらなの」
ちょっと乗ってきた。
「1000円です。野口健が日本も外国人から入山料ヒマラヤ並みにとれって言ってんじゃないですか。長野県独立するんです。富士見で国境管理して入国1人2万円とりましょう」
「党費参政党と同じじゃん。入るよ」
「チョロいな」
投票できなかった外野が冷めて突っ込む。
「いやでも今んとこ宗像さんだけでしょ。もうちょっと大きくなったらやっぱ考える」
「はい、掃除掃除……」
ぼくは連休に山小屋に上がって手伝っている。今年はお盆にも上がって人員が増えた分、ほかのスタッフがお盆休みを取っていた。お盆の15日には、大鹿の南隣の遠山谷の木沢小学校に事務所を置く登山家の大蔵喜福さんを呼んで、「ガイドブックにない道」というテーマで対談イベントを小屋前の東屋でした。ヒマラヤやデナリなど海外の記録を多く持っているけど、今は携帯トイレを普及させての「エコ登山」というのを、大蔵さんは聖岳や光岳で広めている。
南アルプスは3000mの稜線が県境になっている。だけど大蔵さんの話を聞くと、長野県側の遠山と静岡県側の井川では人の往来がかねてからあって、「日本のチロル」と呼ばれる険しい傾斜に、坂畑と家々が散在する下栗の里の人たちも、井川から来たのだという。歩けば沢伝いに2日かかる行程も、焼畑が生業の暮らしでは一連の山並みに見えるのだろうか。
近所に暮らす方が世界中を旅した人でタイ・ビルマ国境のカレン族のことにも詳しく、『森の回廊』という本を貸してくれた。著者の吉田敏浩さんは立川反戦ビラ弾圧のときに取材に来てくれたフリーのジャーナリストで、一時越路の前身の「並木道」も購読してきれていた。
めぐりあわせだなと思って読みはじめると、「少数民族」と呼ばれる人たちが、かねてから暮らすところに国境が引かれ、それぞれの政府から遠い地域は辺境に勝手にされる。それが迫害の理由にもなる。でも人々は、道の真ん中に引かれた国境を縦横に行き来して暮らしている、という。
飯田市出身の大蔵さんも「天竜川の西岸は中央政府が押さえ、東岸は伝統的に反乱軍の拠点」とぼくが飯田の人に聞いた説明をすんなり受け入れて、当日も登山者たちにしゃべっていた。大蔵さんが拠点にする木沢小学校のゆるゆるの雰囲気に「日本の解放区」とぼくが雑誌で付けると、出入りのおじいちゃんたちに大人気の呼び名になっていた。
もはや中央の政党政治が安定的な状況ではなく、選挙結果は民衆が乱世を選んだことを示している。山岳地域に暮らす人々は、世が乱れ、中央権力が割れるとバランスを取る役割を伝統的に果たす、というのは、在野の古代史研究家の藤島寛高さんが言っていたことだ。
大鹿村は後醍醐天皇の息子、宗良親王が30年間拠点を置いた。圧倒的に劣勢の中、「南北朝時代」と呼ばれる時代を画して南朝が生きながらえるのも、山岳地域の住民の支持なくして不可能だった。
朝の掃除の時間、そんな話を布団をたたみながら小屋仲間に話した。
「ああそれミャンマーとかそうなってますよ。軍事政権と民主化勢力、少数民族の三つ巴で争ってますからね。旅行するとあちこちに料金所が設けられて金をとられる」
料金所を設けて活動資金にするというのは、伝統的な反乱軍の手法なんだろう。秩父あたりじゃ、夜中になると暴走族が勝手に料金所作って金取ってるって話を聞いたのは、ぼくが学生のころだ。
とりあえず実行部隊の名称に「伊那谷民族解放戦線」とつけてみた。
(2025.8.22、「越路」46、たらたらと読み切り186)