大分合同新聞で紹介されました。


ライター宗像充のサイト
大分合同新聞で紹介されました。

われらの宗像先生が書いた「二ホンカワウソは生きている」。本書は「二ホンオオカミは消えたか」に続く第二弾。感想文を書いてくれ、ということで本が送られてきた。
まずは著者紹介を確認。「大分県生まれ。ジャーナリスト。一橋大学卒業。大学時代は山岳部に所属。登山、環境、平和、家族問題などをテーマに…」とある。私は途端に不機嫌になった。「これウソじゃん。研究の意味がわからず大学院を中退したことや、最初のカミさんが家出したこととか書いてないじゃん!」。確かに記載されている情報は正しいのだが、宗像君の本質を示す重要な中身が抜け落ちている。この著者紹介では、宗像君がいかにも勉強ができて社会問題にも関心を示す素晴らしい人、みたいにしか表現されていない。ということで、半分ムカつきながら渋々読んだ。
しかし読み進めていくと、中身はそれなりに面白かった。またこれも事実ですな。
この本のキーワードは、「絶滅宣言」と「二ホンカワウソとは何だ」、そして「見ようとしないものは見えない」という三つ。
二ホンカワウソという存在についていろいろな「仮説」が飛び出してくるあたりは、推理小説にも似た論理展開のスリルを感じます。その存在の概念規定に迫るあたりは、哲学的-思想的深みを感じ取ることができる。そしてかつて東京の国立で平和運動に携わり、各種選挙を手伝ったりした「活動家」でもあった著者ならでは感性-国家・社会批判の感性をも感じる。まぁ、こうした感性でものを書くのが宗像君の特徴なんだろうし、だから私みたいなものが読んでも面白いんだろうな。
本書では環境省が出した二ホンカワウソに対する「絶滅宣言」に対する疑問が話の経糸として貫かれている。そこに緯糸としての目撃談や証言がからみながらカワウソという存在に迫っていく。
「国がいないと言えばいなくなるのか。『見かけない』ことは『いない』ことの証拠だろうか。少なくとも言えることは、その判定もまた人間が決めるものである以上、『絶滅』という現象も人間社会の出来事だということだ」(本書P16)。という言葉に、「絶滅宣言」の理不尽さとともに、その存在の有無さえ規定するかのような国家の―社会の在り方に対する怒りを感じるのは私だけであろうか?
また著者はカワウソの激減を論じるくだりで、「話が先走りすぎた」と言いながらこう主張している。
「一瞥してわかるのは、これらはすべて人間が原因を作っているということだ。カワウソは(略)人間が天敵でその活動が大きな減少要因だ。(略)カワウソ減少の理由について『富国強兵』という言葉を使っていた。北方への戦争のための防寒着に毛皮の需要が高まれば、カワウソは高級品として狩猟圧が高まるし、戦後は国内の自然を攻撃することで経済を活性化させることを繰り返していた。だから、もはや経済成長の見込みが立たない時期に、再発見と絶滅宣言が同時に出るのは、何を反省するかという点のやはり分岐点になる」(本書P99)。
そのほかにもベトナム戦争で使われた枯葉剤と薬剤散布の関係を詳説している。著者はこの薬剤散布がカワウソ激減の要因の中で唯一、「関連性をある程度推察できるのがこれだ」と言い切っている。
反戦運動の活動家が書きそうな文句だね。そこが好きだけど。
そして二ホンカワウソの存在が確認できない主要因に、そもそも探さない、というか調査しないという観点を強調している。そう、「見ようとしないものは見えない」のだ。ちなみに、新本格派と言われ現代推推理小説の巨匠でありメフィスト賞第一回受賞者である京極夏彦先生の傑作、「姑獲鳥の夏」もかかる観点がテーマです。そして、著者紹介も「見ようとしない人には見えない」のだよ。
まだまだ、色々書きたいけど紙幅の関係で、この辺で…。最後に、私が本書を読み終えて感じたのは、人間が勝手に殺し、勝手に「絶滅宣言」を出し、勝手に「二ホンカワウソとは?」と論争している間に、とうのカワウソは人里離れたところで悠々と泳いでいる光景。それは人間の浅知恵を超えた自然の力強さの表れなのかもしれない。(難波 広)
追伸。最後に出てくる大月の二人ってエクスペリエンスじゃん!(難波広)
*編集部注 家を出たのは宗像が先です。
「越路」25号、2021.11.11
ひとまず連載は終了。ところがニホンオオカミについての重大情報が・・・。次号さらにご期待。その前に読んでね。


予約はこちらから 読んでね!
すでに絶滅したとされるニホンカワウソ。しかし、今も目撃情報が絶えず、その生存を信じる人たちは多い。2016年、高知県の海岸で〝ニホンカワウソらしき動物〟が撮影されたことに強い関心を寄せた著者は、取材を重ねていくことで生存への確信を得る。環境省の「ニホンカワウソ絶滅宣言」を揺り動かす、渾身のノンフィクション。
予約はこちらから 読んでね!
すでに絶滅したとされるニホンカワウソ。しかし、今も目撃情報が絶えず、その生存を信じる人たちは多い。2016年、高知県の海岸で〝ニホンカワウソらしき動物〟が撮影されたことに強い関心を寄せた著者は、取材を重ねていくことで生存への確信を得る。環境省の「ニホンカワウソ絶滅宣言」を揺り動かす、渾身のノンフィクション。
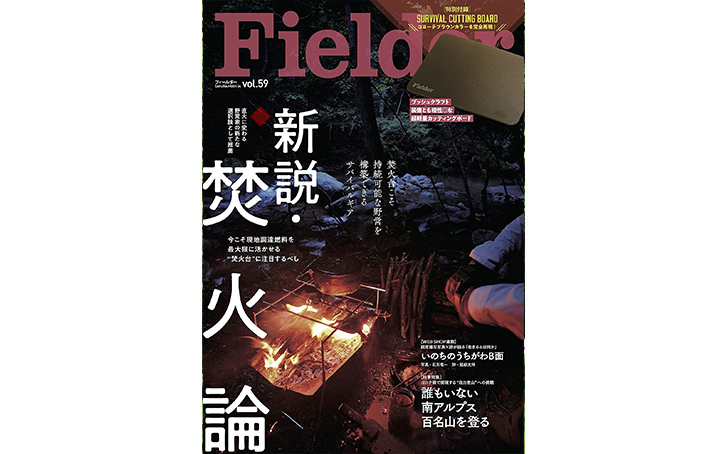
第19回 二つのグループのニホンオオカミ
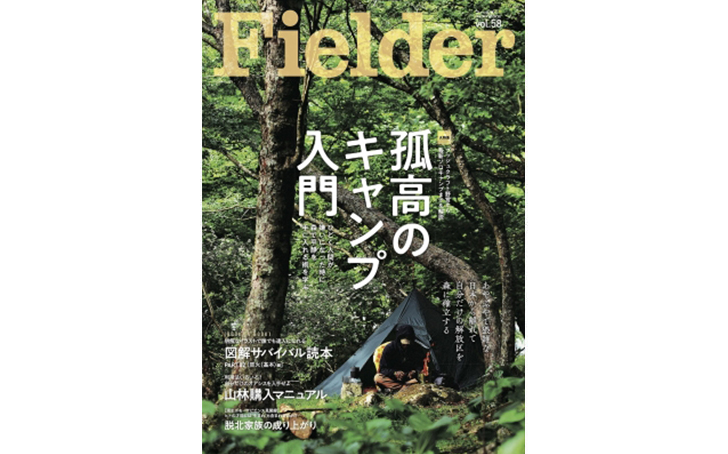
第18回 ニホンオオカミはなぜ消えたか?

「絶滅」野生動物生息記―ニホンオオカミ編
第17回 ニホンオオカミはオオカミなのか?
