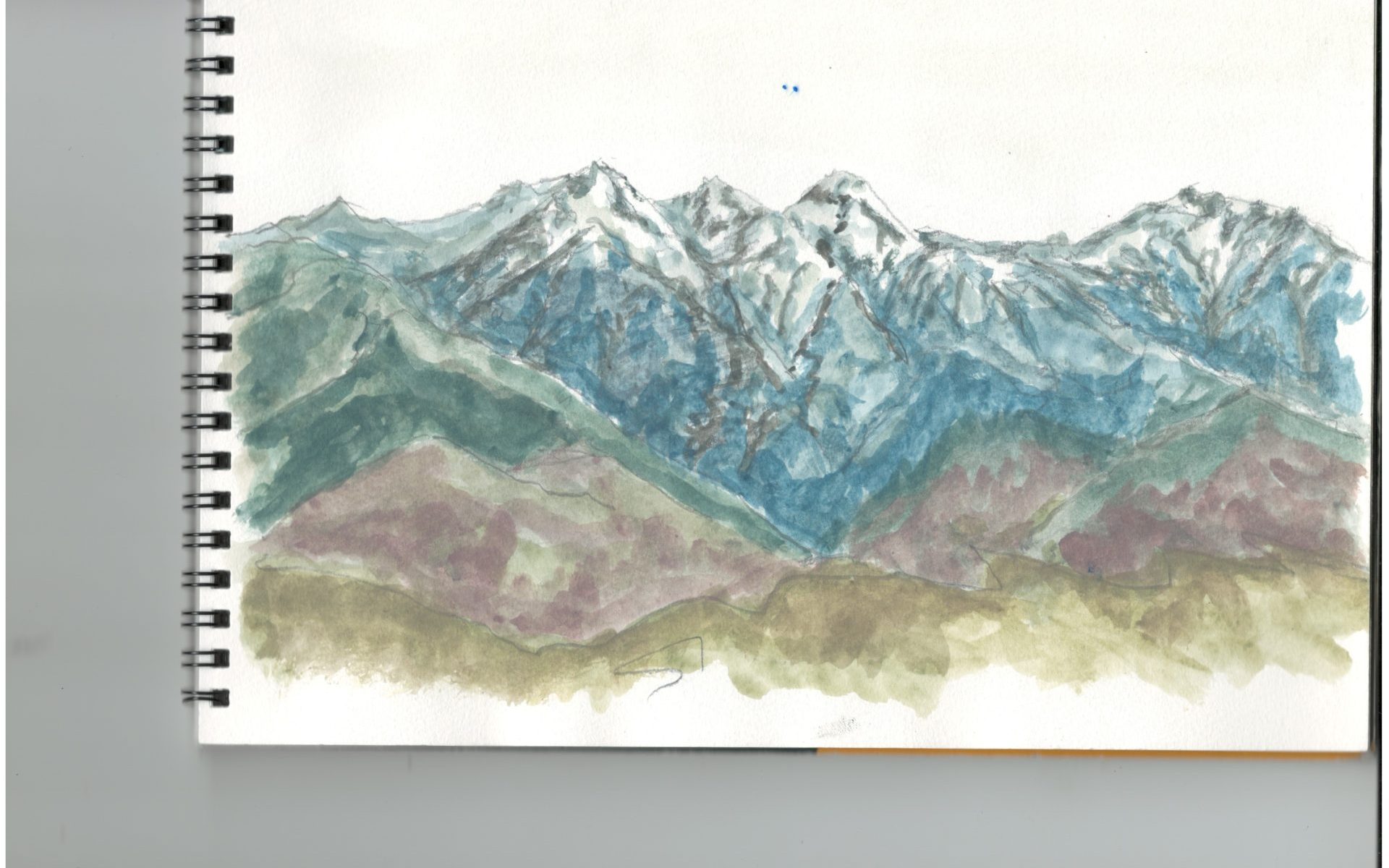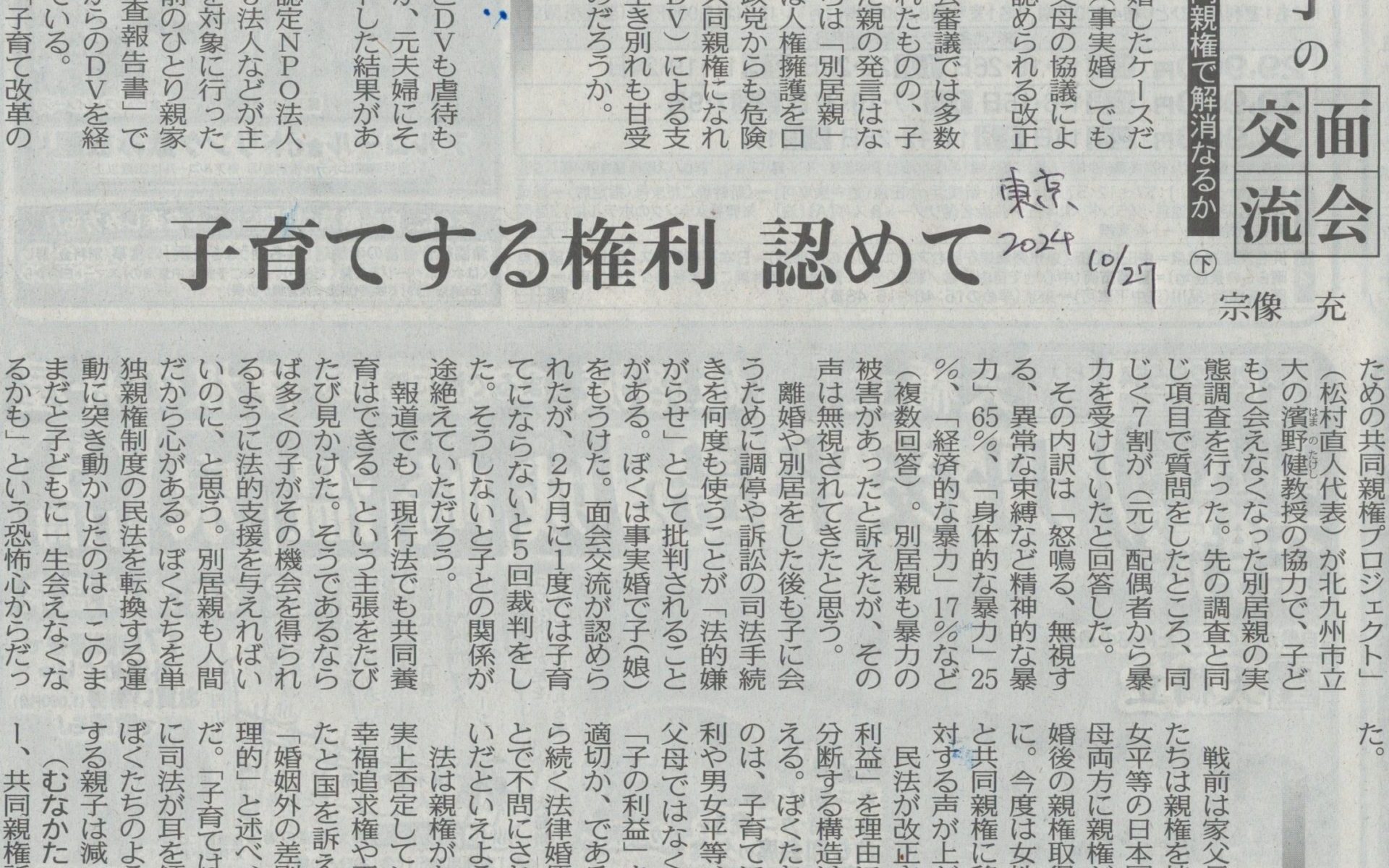この記事は手作り民法・法制審議会(共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会)が作成した大鹿民法草案(改正手づくり家族法草案)のあとがきです。草稿を書いたのでここで公開します。
手づくり民法・法制審議会の発足
昨年2021年から法務省は学者や識者を招集し、家族法制の見直しを掲げて、現在の親権制度の改革案を議論しはじめた。この夏には中間試案を公表し、パブリックコメントを募ることが報じられている。
私たちは、手づくり民法・法制審議会という有志の集まりである。法務省の法制審議会委員は、23人中4人が法務省民事局、裁判官からなり、幹事においては過半が官僚である。諮問するほうが諮問されるほうで法を作るという官製委員会である。昨年の法制審議会の議論を見て、現行制度を維持しながら国際的な批判をかわすための体裁を整える事務局側の狙いが明らかだったため、私たちは独自の議論の必要性を感じ、人権や男女平等の観点から国の法制審議会に勧告を出し続けていた。
というのも、私たちの多くは、男女の別れをきっかけに、子どもと引き離される経験を持っているからだ。私たちはそのつらい経験の中から、司法や法制度による人権侵害や不平等について考えるようになった。それに対し声をあげる中で、多くの識者や専門家、また多様な立場の「当事者」と呼ばれる、生きづらさを抱える人たちと議論する貴重な機会を得た。この貴重な機会を生かすべく、私たちは、私たちにしかできない現場目線の民法草案の取りまとめを試みた。
一方、民間の有識者や法律家たちは、民間法制審の中間案を公表している。彼らの中間案は、実子誘拐や親子引き離しについて、国の法制審が解決し、むしろそれらを合法化する危険性について警鐘を鳴らす。それらの指摘は多く的を得ている。婚姻外の単独親権制度という現行の政策に対し、一部の人権への配慮を示しつつ、離婚後の秩序を国際水準に合わせ定めるということは一定の評価に値する。
ただし、実は諸外国はbiological parent(実父母)と子との関係を保障するために親権が規定されているため、「婚姻」と「親権」とは分離されている。言い換えると、「実親」と「実子」との関係を規定しているのが諸外国の「親権」であり、だからこそ婚姻状態に関わらず「実親」が「親権」を有し、剥奪されるような場合は例外である。
こういった“そもそも親権とは何なのか”という、一般市民の誰もが共通認識を持てる概念の前提を置かなければ、「裁判所は子から親、親から子を奪うことができるのか」という、誰もが頭に浮かぶ疑問への回答に答えることは困難である。
親の道徳感とみなし子の生産社会
「子どもの最善の利益」を共同親権が確保するという議論は、共同親権を求める人々の中に根強くある。一方で、家庭裁判所が親子を引き離してきた理由付けもまた「子どもの福祉」である。これらは、共同親権であれ単独親権制度であれ、どのような親が子どもにとってふさわしいかを社会の道徳観が決めてよい、という点で共通する。
一方、私たちの中には現在、単独親権制度の違憲性を主張し、国を訴えている者もいる。その主張は、子どもにとって何が利益かをまずもって判断するのは親であり、そのために親権という様々な権限と義務が法律によって定められるというものだ。もちろん、親も子も国や地域あるいは血縁関係の中で生きていて、何が子どもにとって利益かという判断は、親によってさまざまに違う。しかし、国が親に先立ってその判断の是非をすることを許せば、親による子育てが国の判断でできなくなっても、文句は言えない。
私たちの中には、「子育て改革のための共同親権プロジェクト基本政策提言書」の策定に関わった者もいる。その議論の中でも、親の権利と養育責任の明確化、そして単独親権制度の廃止を、基本政策として掲げた。単独親権制度の廃止という言葉は強いが、婚姻外においては、単独親権しか許されない制度を廃止することによって、双方の親による子育てという原則が明確になる。一方、親による養育責任だけを強調すれば、社会環境の中で子育てができない親を、不適格な親として養育から排除することをやはり許してしまう。
国の法制審の議論は、子育ての第一義的な責任が父母にあることすら軽視している。一方、民間法制審の中間試案では、「親子水入らず」を強調することで、家族の負担が高まることになってしまわないか私たちは気にかけている。道徳感として養育環境を十二分に整えられない親は、子育てをする資格がないとみなされてしまわないだろうか。
子どもが両親と過ごし成長する権利は、国の法制審では議論すらされたことがない。これらは、親どうしが子どもへの関与を示さない場合、みなし子を量産することを制度的に許すことにもつながる。養子縁組の斡旋に努めるNPOのリーダーが、これを可能とする共同親権制度に強力に反対するのはそのためである。
一方、親の権限強化だけを強調すると、児童虐待が蔓延する中、子どもの権利を損なう親の判断も許容されてしまうという危惧もある。もちろん、子どもを親とは別の人格として認めない様々な行為は、今日その意識の高まりとともに虐待として指摘されるようになっている。そのために必要な国の介入も適切になされるべきだ。
しかし、家族の「自己責任」が強調される中、親の権利が曖昧なままでは、その権限を制約する適正な手続きも保障する必要性は低く、結果的に児童虐待への司法介入が諸外国に比べて極端に少ない一方で、行政介入に歯止めがかからない原因となっている。そのまま子どもと生き別れてしまうことも社会問題として指摘されている。周囲に後ろ指を指されないようにびくびくしながら子どもを育てる姿を、多くの家族で見ることができる。例えば少々活発な子どもを、育てにくい子として、多動(ADHD)のラベルづけを行い療育機関に通わせるように学校が親に求め、その結果として父母の意見相違が生じた時に、耐えられない家庭は離婚などによって破綻する。
「親は子どもに親にさせられる」
子どもとともに過ごすことによって、育まれる親としての実感・喜びのない子育ては権利とは呼びがたい。しかし、子育ての権利性を認めない社会は、養育費だけ払えば責務を果たしたという、子どもにとっては通用しない理屈で、寂しさを抱える子どもたちへの配慮が著しく欠けている。
親が子どものためにする判断は、子どもが親と過ごす中で得られる安心できる幼年時代を親や周囲が確保する中で、はじめて権利として意味を持つ。一方、国がその権利を認めるならば、親の不適切な行為に対してペナルティを課すだけでなく、子育てを権利と感じるだけの養育環境を、国が整える責務が生じる。国の責任放棄が問われないようにするために、親の権利を否定し家族に責任だけ押し付けたところで、子どもは笑顔になれはしない。
結婚はぜいたく、家族は苦役
私たちが目指しているのは、国と地域と家族が、それぞれ得意なことを出し合いながら、多くの人に見守られる中で子どもが育つ社会である。その社会では、地域に子どもの姿が当たり前に見られ、子どもの笑い声を「騒音」と迷惑がったりしない。今日では、社会で子どもを育てることを社会的養護と呼んだりする。しかしそれが、親を排除することで実現するなら、それは「みなし子」生産社会に過ぎず、子どもの笑顔は期待できない。
何よりも、親にだけ子育ての責任が押し付けられる社会では、親は必死で養うためのお金を稼がなければならず、効率性を維持するための性役割的な子育て体制に適応するしかない。こういった家族と社会のあり方は、国の力を増すことで富を分配できていた時代には妥当性があったかもしれない。戦争や経済成長は、「男は仕事、女は家事育児」という画一的な家族モデルに適合的で、夢を持った人たちは都会に居場所を求め、結婚すれば団地がその場を提供した。それが「正社員的な家族」のあり方であり、「入籍」と呼ばれる結婚は、称号として機能した。
家族法もまた、自足的な家族モデルに適合的な規範を維持すれば用が足り、それ以外の家族のつながりは軽視した。家族のつながりを絶って顧みない単独親権制度は、個人個人が家族のつながりよりも、国に奉仕する家族の形に個人を適用させるために、必要なものでもあった。このことは、富国強兵を目指した時代の明治民法の制定経緯からも明らかである。
ところが、このような家族モデルを今日得られるのは一握りの勝ち組である。民間法制審は、子どもを連れ去られるとわかっていたら、男は怖くて結婚できないと指摘する。それは一面では正しいが、生涯未婚率が向上している現代において、統計から生涯未婚率と男性の年収に関係があることが分かっている。高年収でない限り結婚ができない、つまり(女性の側からはそういった男性をつかまえられたという面でも)結婚は勝ち組の特権であり、ぜいたく品と化したことが、男女ともに若者たちが結婚し家族を持つことを敬遠する理由だ。経済成長が期待できず、所得も上がらず家族もまた分配にありつけなくなった時代、特定の家族モデルに全ての個人を当てはめるのは限界がある。
法律婚をして子どもをもつのが一人前の証。同一姓の戸籍はその称号。第3号被保険者や配偶者控除で主婦を家庭に抱え込み、男に稼ぎを期待する。離婚には次の形を整えるために、単独親権で家族のつながりを絶つ対応がなされた。子どもが二つのイエ(戸籍)に所属する共同親権は都合が悪いからだ。形を壊すのは社会的な落伍を意味するから、DVやモラハラがあっても耐え忍ぶ。この家族モデルは、常に落伍の恐怖を抱えながらストレスを再生産する、不安醸成装置であり、家庭生活は苦役にほかならない。
安心が得られる結婚、子育て
結婚に積極的な意味をこれから求め続けるとするなら、多分今のままだと無理だろう。こういった結婚制度の内実がわかって、今時進んで希望する若者が多いとは思えない。離婚後の共同親権を定めて実子誘拐を禁止することだけでは、状況はさほど変わらないのではないか。
結婚は、戸籍によって制度化されたイエと密接に結びついている。結婚はイエとイエの結婚だから個人の勝手で離婚は本来許されない。しかし結婚も離婚も、個人が幸せになるための選択=権利だとするならば、私たちはそれがともに安心を得られるものでなければならないということに気づく。入籍することで一体感を求められ、団体の中は実力行使で力の強いものの意見が通り、後は同調圧力でみんなが従う。言うことを聞かなければ仲間外れにして排除する。それは何も家族に限らず、日本の多くの組織で見られる特徴だろう。
しかし、元々夫婦であっても、そして親子であってすら、人格を別にするという点で、家族は他人である。元々意見や考えが違う者同士が共同生活を営むことを選ぶのが結婚なら、それを前提にした意思決定や問題解決の仕方を国が用意しておかなければ、家庭生活自体が常に不安にさいなまれるのは当たり前すぎる帰結だ。
この点、日本の民法は婚姻中のみに共同親権を付与して、子どもがいる場合における共同意思決定を法律で定めている。しかし、子育ての場として家庭が期待されながら、平等な二者どうしの意見が分かれた場合の解決方法が規定されていないため、意思決定が不能に陥る。そして離婚して一方から意思決定をはく奪することしか法的には用意されていない(単独親権制度)。共同親権は親権の調整規定があってはじめて機能する。この点についての規定がない日本の民法は、世界的に見ても類を見ないものであり欠陥制度である。しかしそれが可能なのは、共同親権もまた姓と同様、結婚の称号だからにほかならない。
地域に子どもを取り戻そう
私たちは、戸籍(イエ)制度に取り込まれた結婚を、個人の権利の問題として捉えなおすことが最低限求められると考える。家庭を大事にする個人の考えはもちろんあってしかるべきだが、その道徳を法によって個人に押し付けるのは本末転倒である。婚姻外の単独親権規定を廃止することによって、婚姻内外問わず共同親権を原則とすることが、法的には、個人間のパートナーシップへの国の支援のあり方として求められる。戸籍は本来家族関係を登録するための手続きにほかならない。ここで代替的な登録方法を提案するのが目的ではないが、手続きのために個人間の家族関係を法的に定めるのもまた、本末転倒である。
この点、国の法制審の事務局提案は、この本末転倒な理論によって民法改正案を考案することを目的としている。もとより、1947年に日本国憲法に適合的に応急的に定められた暫定民法(日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律)(参考4)は、すべての子どもが親の保護を受けられるために、婚姻内外問わず共同親権を適用している。共同親権が両性の平等と個人の尊重に適合的な制度であることは、75年前にすでに法務・司法当局によって確認されていたことである。原則に立ち返るべきことだ。
このことによってはじめて、国も世帯単位ではない、個人や家族的関係に対する配慮や支援がしやすくなる。出生や結婚など、個人の法的地位の誕生や変動、個人間のパートナーシップに対して、届け出を受理するという形で自治体が選別して登録を制限することは、個人のための登録手続きという観点からすれば、やはり本末転倒だ。
結婚によって家庭を築くことや、離婚・未婚時には共同親権を確保して、親の子育てが権利となる環境を整えることは、国の責務であり、法整備はそれよる支援の一環である。子どもは大人のように自活することはできない。しかし一個の人格としての子どもに目を向ければ、子どもが生きていくのに必要な資金を提供することもまた、子どもの成長に必要なことであり、健やかな家庭生活を営むにおいて望ましい。
一方、親だけでなく、地域的なつながりの中で生きていくことも子どもの成長において必要である。現在、子育てをする際、子どもは親の仕事、つまり社会的な生産活動の邪魔者としてしかとらえられておらず、保育園や学童保育などに隔離される傾向がある。その結果、都会や田舎双方で子どもは地域から姿を消している。親が子どもを抱えきれなくなれば、更に児童相談所から児童養護施設へと収容が進む。
親が男女ともに、子育ての経済的な負担から解放されることによって、親には子どもに直接目をかける時間が生まれる。必死で稼ぐ必要もないので、男性が育休をとる環境も整えられる。特に子どもが小さい場合、その時間はかけがえのないものだ。もちろん、経済的な余裕が生まれることによって、親は保育所も含めて一時的な委託先(親類、知人、ベビーシッターも含めて)を活用することもできるし、時間的な余裕は、社会活動や子育てに必要な人のつながりを形成する機会を得ることもできる。それは地域が子育てしやすい環境へと変わっていくきっかけになるだろう。
親だけが子育てをするのではない。大人たちは、たとえ自分に子どもがいなくても、子どもが身近にいることによって、学び成長する機会を得られる。それは弱者にやさしい地域づくりにもなり、地域の活性化の一助ともなる。それは子どもに国が投資するにおいて、社会的な合意を育む基盤となる、環境整備でもある。