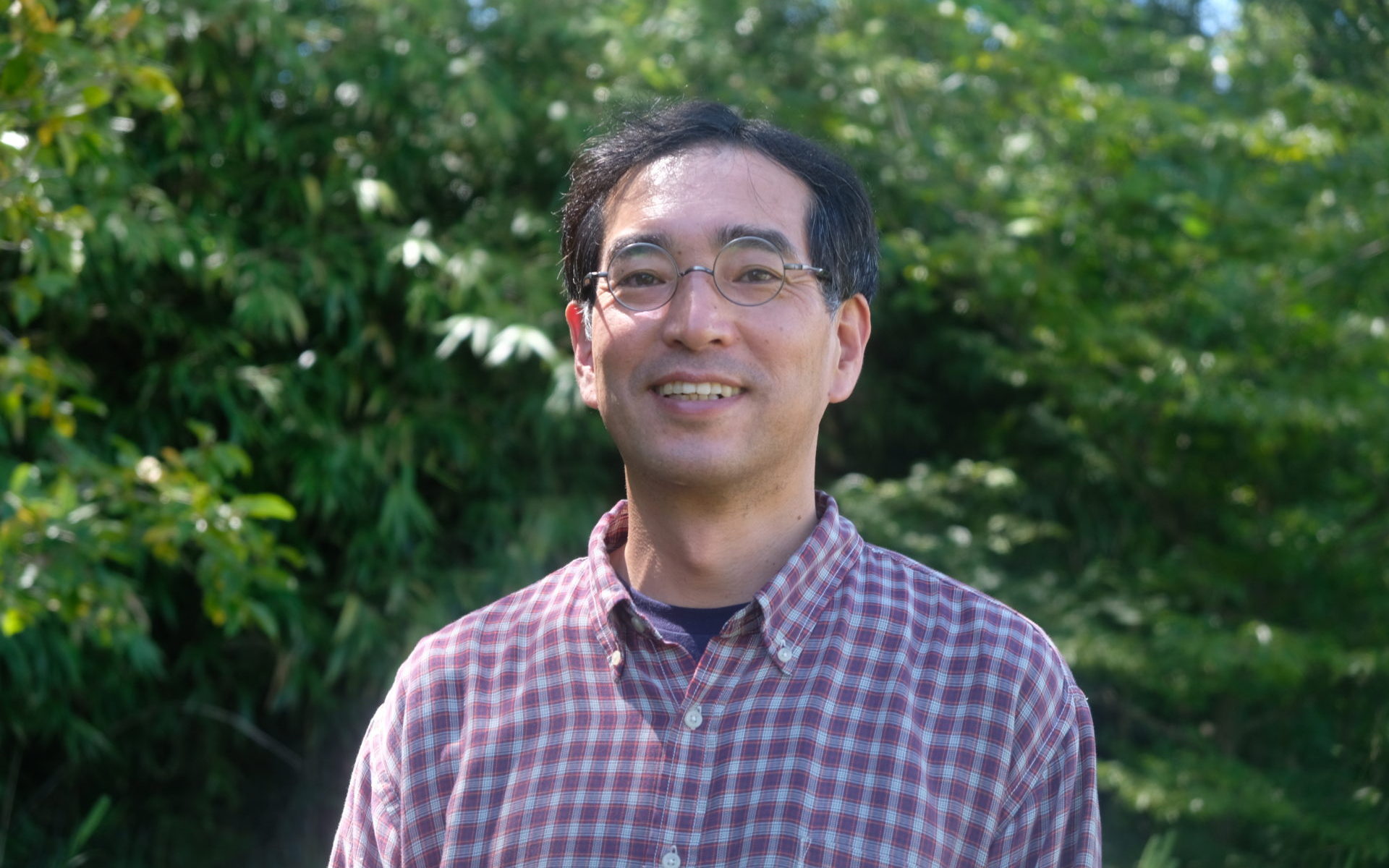今年5月、民法が改正され、親権法については77年ぶりに見直しがなされた。長らく単独親権から共同親権への民法改正を求めてきた一人として複雑な気持ちで法案成立を見届けた。
ぼくが立法不作為の国家賠償訴訟を提起してまで法改正を求めてきたのは、自分の子ども、娘に会えなくなったのがきっかけだ。しかし、今回の法改正でその道筋はいまだ見えない。
事実婚の非婚の父として娘を育て、妻と分かれる際、一時娘を見ていたときに、妻からの人身保護法による子の引き渡し請求で司法はぼくを「拘束者」とした。2008年のことで「親権がないから」との理由だった。
元妻の側が「会わせる」と提案して面会交流の合意書を交わし、娘を渡すと、娘は元妻の再婚相手の養子にされ、会えなくなった。
当時、東京で子どもに会えない親たちの自助グループがあり、参加した。自分は例外ではなかった。日本は離婚に伴い親権を父母どちらか一方に定める。海外の共同親権の国では、父母が別れても双方で子育てし続けると知った。
しかし、日本で司法に訴えても面会交流の約束を取り付けられるのは5割。それも会える保障はない。実際、ぼくは司法の決定が出るまで2年半、娘と引き離された。ぼくと娘の前に立ちはだかったのは法だった。
裁判所ではいまも元配偶者(やその夫)がマジックミラー越しに監視する中、子と会うよう仕向けられており、ぼくも体験した。母親側の意向に背いてまで会わせる石は司法にない。娘と会う場面に元妻の再婚相手が監視をしに現れ、そのことを裁判で養育への妨害だと主張すると、司法は「親権者だから」と容認する。「会いたかったら運動をやめろ」と親権者が子を用いてする人質取引を司法はとがめることはない。
面会交流の決定は2カ月に1度、2時間のみ。それを月に1度にするのに、さらに4度裁判をした。間に挟まれるのに疲れた娘は会いに来なくなり、ぼくは月に1度、娘が暮らす家を訪問して手紙を投函した。
これだけ書くと「何か理由があったんでしょう」と言いたくなる人はいるだろう。理由があるのは当然で、それを何とかするのが法だ。共同親権はいまの単独親権で自分の子と会えなくなるという絶望を経験した多くの親にとっての希望だった。ぼくは仲間と法改正を拒む国を訴え、国は法制審議会を開き、ようやく民法が変わった。
改正民法は子と離れて暮らす親が負担する養育費の徴収強化は立法化し、親子の再統合の規定は見送った。司法で情勢が親権を取る割合は94%に上る。不公正な司法慣行の立法化だ。改正民法のメッセージは「会えなくても金は払え」。露骨な性役割を前提にしたものだった。