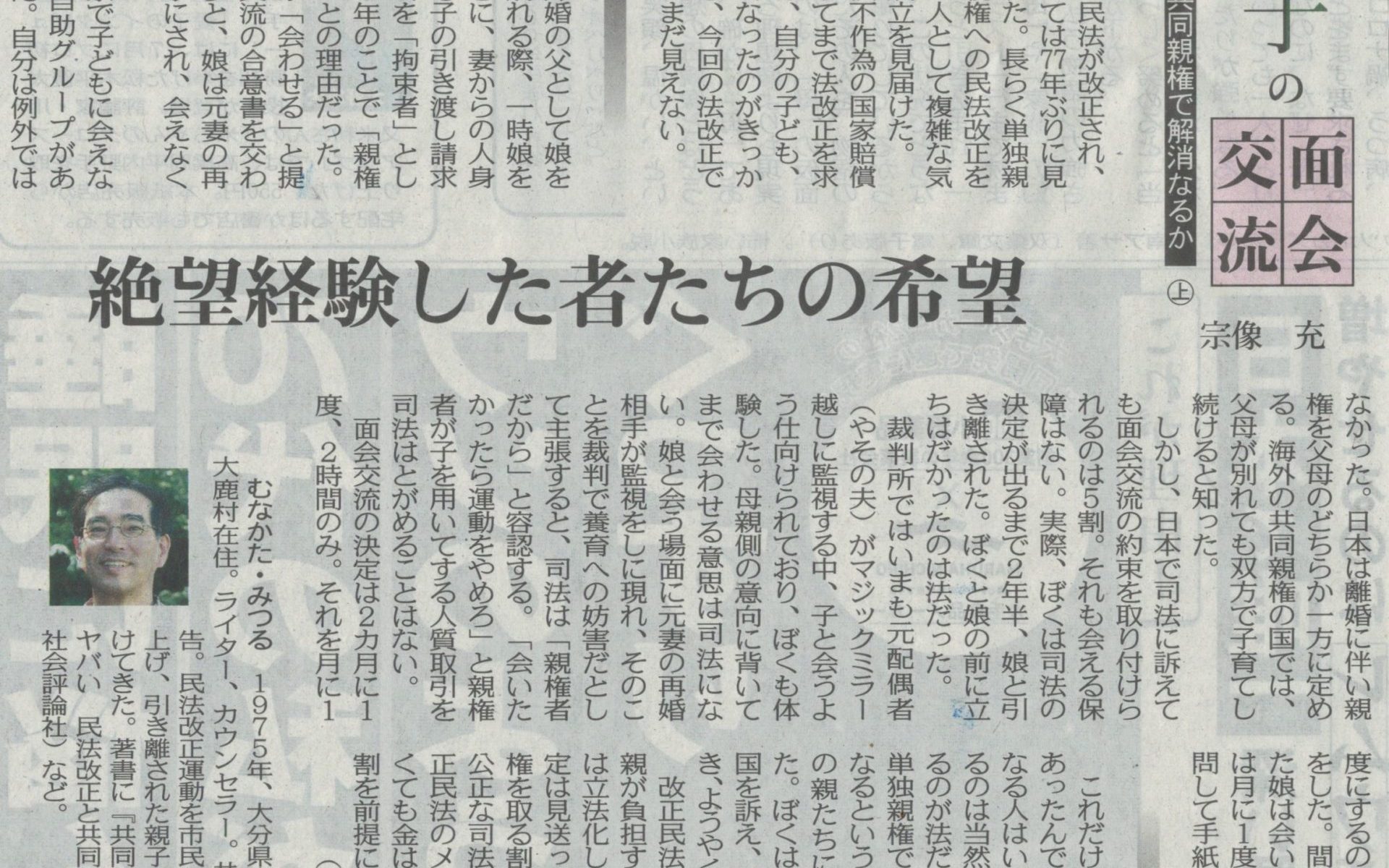東京新聞の日曜版の上下2回のコラムで10月13日と27日、共同親権の民法改正と、子どもに会えない親たちで提起していた共同親権訴訟について触れる原稿を書いた。ところが年が明けて2月2日と9日、東京新聞は弁護士の太田啓子に、ぼくの書いたコラムの内容を真っ向否定する記事を書かせている。
その後東京新聞(中日新聞)には事実関係について確認し、経緯を明らかにする質問を送った。まともな回答は来なかったため、原稿料を大島宇一郎社長宛に返却した。その経過をまとめる。
共同親権と真っ向勝負していた東京新聞
10月に掲載予定のコラムに東京新聞の知り合いの記者のAさんから原稿依頼をされたのは、昨年6月のことだ。東京新聞は中日新聞東京本社のことなので、以下は東京新聞とし必要に応じて中日新聞と言及する。
コラムは「人生のページ」というもので、後に東京新聞に出した質問状の回答によれば「人生について考えるきっかけとなりそうな話題やテーマを、さまざまな立場の方に、ご自身の生き方や体験などを踏まえて書いていただき、読者に提供するというのが趣旨」だ。ぼくもその趣旨に基づいて原稿を用意している。
コラムを担当するAさんとは、2008年に国立市議会への陳情活動から始まった法改正運動の初期に取材していただき、何度か特報欄で問題提起してもらっている。当時の記者でその後も何年も運動の会報誌の送付を続けてきた方は何人かいる。Aさんもその一人だ(唯一会費の納入をしてくれていた)。
ぼくの友人は東京新聞の読者だけど「ある時期まで賛成反対両方載せてたのに、ある時からピタッと賛成の記事はやめたよね」とぼくに言ったことがある。一般読者が気づくくらい東京新聞の方針変換は露骨だったようだ。あるとき社内研修で共同親権反対の旗頭の岡村晴美を呼んで以来のことのようだ。
ぼくもこのことは聞き伝えていて、親子の引き離しという人権問題を度々イデオロギー対立の問題にすり替えて、もみ消してきた東京新聞の報道姿勢をSNSを中心に批判してきた。小林由比、大野暢子などの女性記者名をよく見た。だからこそそこに書く意味があると、原稿を引き受けた。
書くにあたっては、原稿依頼がされた後、2024年8月2日の「あの人に迫る」という小林由比記者による岡村晴美への「DV被害を軽視 危うい共同親権」というタイトルのインタビュー記事を参照した。
一連の東京新聞記事では、ぼくたち子どもに会えない親をとにかく危険視し、ぼくたちの側への取材を一切しなかった点では徹底しており、故にコラム欄とはいえぼくの記事はそれに対する対抗言論としての意味合いもあったからだ。
2回目掲載に至るまでの攻防
1回目原稿が出たのが10月13日。
通常このコラムは2週連続で記事を載せ、東京新聞だけでなく中日新聞管内でも掲載される。1回目記事が出た後、多くのクレームが会社に寄せられたのをAさんから教えられ、後編記事の改変に取りかかることになる。というのも前半記事が出た時点で後編記事はすでに書き終え校正も終えていたからだ。
念のため言っておけば、ぼくは登山の雑誌がモンベルに移管するまで東京新聞発行の岳人に長らく編集者・ライターとしてかかわってきた。そのため先の岡村の研修も含め、社内事情はAさんだけから得るわけではない。
とはいえ今回の原稿はぼくは外部の人間として依頼された側なので、読者の反応を受け改変するにしてもぼくのほうにも言い分があり、あまりに失礼な内容については「改変はいいけどぼくの名前は消してくれ」と、「抵抗」してもいる。
人生のページというだけに、ぼくの原稿は子どもと引き離されてから今日に至るまでの経過も触れている。その内容自体は過去の東京新聞の記事や他の報道でも紹介されることがあった。しかしAさんは、審判の決定文を見せてくれという社内の意向を伝えてきた。どうもクレームの中に暴力の加害者に書かせるのかという批判が含まれているようだ。
この点についてぼくは、元妻を引っぱたいたことがある点については隠していないし、過去公にしてきた。それを自分の手記で出版して出しているので、暴力の加害者に書かせるのかという批判は、被害者の訴えではなく加害者の独白から来ているので意味がない。
しかし新聞社はそうではないようだ。刑務所暮らしした人や横領政治家のインタビューは載せても、女性に手を出す人間は無条件に人間外の存在になる。第三者の人間関係にまで自分たちの価値観を押し付けて断罪し、当事者間の関係を損なう。この場合被害を受けるのはまずもってぼくの子どもだろう。
東京新聞の取材不足が露呈
とはいっても、ぼくが見せた審判書きでは暴力が争点になっておらず決定でも言及がない。彼女の側も相当のことをしていて、しかもぼくの友人と家庭を作って養子縁組して子を引き離しているので、司法も同情しにくかったという事情もある。現在ぼくは性や加害被害を問わない脱暴力支援を行なうカウンセラーでもある。
この審判書きは担当部長も目を通して、以後「原稿を依頼された側」というぼくの立場に配慮を示すようになっている。「こんなに苦情くるの望月衣塑子以来」とAさんに教えられた。
苦情の中身は質問という形で列挙され、その内容はぼくのホームページで後に抗議文を送った際に同時に公開している(https://munakatami.com/blog/chunichikougi/)。
この内容を見ると、東京新聞内部では再婚養子縁組で司法が面会を制約するとか、マジックミラー越しに元配偶者が監視する中で試行面会が行われるとか、人質取引がされるとか、2月に1回の面会を増やすのが通常はあり得ないとか、離婚や面会交流の実態について調べればすぐわかるような初歩的なことも共有されていないことがよくわかる。Aさんもそれはわかっていたようで「取材してないんですよ」と憤りつつぼくに伝えてきている。
ぼくは馬鹿正直にこれらについて口頭、文章で回答し、まとめるとA 4で10枚は超えている。Aさんもそれを取りまとめるのに多大な労力を費やしたようだ。東京新聞内部の数年分の取材不足のつけをぼくたちが払わされた格好だ。
Aさんは「一週間こればっかりしている」と愚痴っていた。