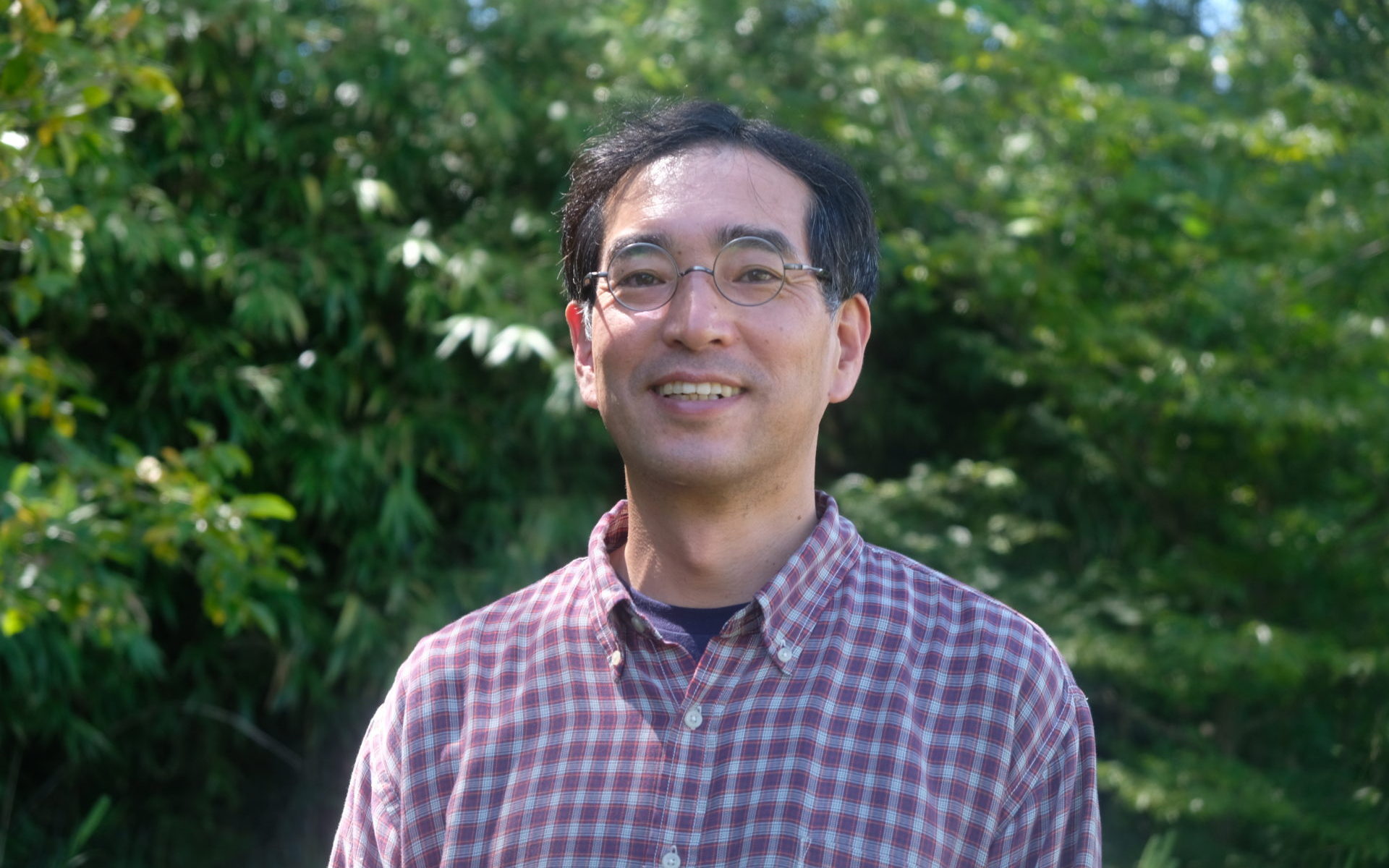この5月、離婚したケースだけでなく、未婚(事実婚)でも父親が認知し、父母の協議によって共同親権が認められる法改正が成立した。
民法改正の国会審議では多数の参考人が呼ばれたものの、子に会えなくなった親の発言はなかった。ぼくたちは「別居親」と呼ばれ、日頃は人権擁護を口にする人たちや正統からも危険視されている。共同親権になれば家庭内暴力(DV)による支配が続くから、生き別れも甘受せよとでもいうのだろうか。
現行民法のもとDVも虐待も増え続けているが、元夫婦にそれぞれアンケートした結果がある。
2020年、認定NPO法人フローレンスら3法人などが主に女性ひとり親を対象に行なった「別居中・離婚前のひとり親家庭アンケート調査報告書」では、72%が相手からのDVを経験したと回答している。
一方2022年に「子育て改革のための共同親権プロジェクト」(松村直人代表)が北九州市立大の濱野健教授の協力で、子どもと会えなくなった別居親の事態調査を行なった。先の調査と同じ項目で質問したところ、同じく7割が(元)配偶者から暴力を受けていたと回答した。
その内訳は「怒鳴る、無視する、異常な束縛など精神的な暴力」65%、「身体的な暴力」17%など(複数回答)。別居親も暴力の被害があったと訴えたが、その声は無視されてきたと思う。
離婚や別居をした後も子に会うために調停や訴訟の司法手続きを何度も使うことが「法的嫌がらせ」として批判されることがある。ぼくは事実婚で子(娘)をもうけた。面会交流が認められたが、2カ月に1度では子育てにならないと5回裁判をした。そうしないと子との関係が途絶えていただろう。
報道でも「現行法で共同養育はできる」という主張をたびたび見かけた。そうであるならば多くの子がその機会を得られるように法的支援を与えればいいのに、と思う。別居親も人間だから心がある。ぼくたちを単独親権制度の民法を転換する運動に突き動かしたのは「このままだと子どもに一生会えなくなるかも」という恐怖心からだった。
戦前は家父長制のもと、女性たちは親権を持てなかった。男女平等の日本国憲法の施行で父母両方に親権が認められた。離婚後の親権取得率は女性が9割に。今度は女性や子どもを守れと共同親権に移行することに反対する声が上がった。
民法が改正されても、「子の利益」を理由に司法が親と子を分断する構造は変わらないと考える。ぼくたちが問いたかったのは、子育てにおける父母の権利や男女平等、そしてその子の父母ではなく司法が一方的に「子の利益」を反するすることは適切か、である。それは戦前から続く法律婚優位の家制度のもとで不問にされてきた数々の問いだといえよう。
法は親権がない親の権利を事実上否定している。父としての幸福追求権や平等権を損なわれたと国と訴えた。1、2審は「婚姻外の差別的取り扱いは合理的」と述べ、最高裁に上告中だ。「子育ては権利だ」との訴えに司法が耳を傾けさえすれば、ぼくたちのようなつらい思いをする親子は減っていくだろう。