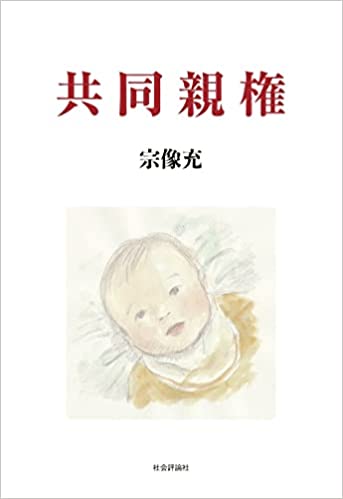このところ、共同親権や実子誘拐のテーマについて、報道機関に対し学者も含め口封じの圧力がかかっていて、新聞記事やテレビニュースにならない状況が続いています。
つきましては、声明文に多くの方のご賛同のお名前をいただくことで声を上げることを目的に、以下の内容で賛同を集めたいと思います。ご一読いただき、ご協力いただけますよう、よろしくお願いします。拡散歓迎です。
■賛同〆切 3月31日(木)
■賛同送付先 kuchifujino@gmail.com
ご賛同いただけます方は、以下の空欄に記載いただき、メール連絡先まで送付下さい。
個人、団体とも可です。お名前(団体名)と肩書を公表します。連絡先(メールまたは電話)は不明点の問い合わせのためです(公表はしません)。
いただいた賛同は、記者クラブほか報道各社に届けて記者発表するほか、呼びかけ人のサイト、SNS等で公表します。
お名前(or 団体名)
肩書
連絡先(メールまたは電話)
呼びかけ人
石井 政之(ノンフィクション作家)、田中 俊英(一般社団法人officeドーナツトーク代表理事)、西牟田 靖(ノンフィクション作家)、牧野
佐千子(ジャーナリスト)、宗像 充(ライター)
問い合わせ 0265-39-2067(宗像)*不在時は留守電に電話番号を残してください。
* * * * * 以下声明文案 * * * * *
実子誘拐・共同親権に関する公正報道を求める共同声明(案)
2022年2月21日、警察庁は各都道府県警宛に「配偶者間における子の養育等を巡る事案に対する適切な対応について」という文書を出しました。
親による子どもの誘拐について、場合によっては刑事罰の対象になることを示した判例とともに、同居時からの連れ去り、及び別居親による連れ戻しについて、被害の届出について適切に対処するよう求める内容です。
日本以外の諸外国では、“child abduction”実子誘拐として処罰の対象になる行為が、日本では放置されてきました。
この現状の中で、先の警察庁通知の持つ意味は大きく、内容の是非の議論はあるにしても、夫婦間の関係が悪化した場合において、どのような対処が法的に規制されるうるかについての規範の変更ともなりうるものです。
しかしながら、国民生活において大きな影響を与えるこの通知について、一部のネットメディアを除いて、その存在を公にして報じた新聞社、放送局は現在まで見当たりません。
過去、実子誘拐や共同親権についての記事が掲載され、番組が放送されると、大量の苦情がメディア企業に寄せられ、その中でネット上の記事が削除されることも見られました。問題となる記事や番組は、男性が加害者、女性が被害者という従来の報道姿勢に挑戦するものです。
また先の通知に関して報じたネット記事が掲載されると(「AERA」朝日新聞発行)、修正されたことが記事中に明示されました。この記事に関して、詳細な正誤表がSNS上に出回り、記事を残すために言い回しまで忖度する編集サイドの姿勢がうかがい知れます。
これからの社会で、どのような制度や社会認識が作られていくのか、受け手が判断できるよう賛否両論についてメリット、デメリットを適切に報じ、さらにそこで出された論点の妥当性について評価しながら議論に資するのが、報道機関としての役割です。
にもかかわらず、ことこの問題については、苦情が来そうなので触れない、というイージーな判断を報道の公共性に優先する大手メディアの姿勢は明らかです。
このような姿勢が変わらなければ、公正な報道を続けようと奮闘するネットメディアの記事も孤立します。もはや報道機関全体が信用を失墜し、その役割を果たせなくなるのではないかと私たちは危惧しています。
社会にタブーを広げているのは、口封じのためにあなた方の会社に苦情を入れる人たちであり、同時に、マスメディアで働くあなたたち自身です。双方の主張の違いを人権侵害行為を報じない免罪符にしてはなりません。
私たちは新聞社や放送局が、男性を加害者としてのみ扱う報道姿勢を改め、実子誘拐や共同親権についての報道について、もっと積極的に取り上げることを求めます。
それは伝えるべきことを伝えるという本来報道に求められる役割にほかなりません。
呼びかけ人
石井 政之(ノンフィクション作家)
田中 俊英(一般社団法人officeドーナツトーク代表理事)
西牟田 靖(ノンフィクション作家)
牧野 佐千子(ジャーナリスト)
宗像 充(ライター)
Fielder【Vol.62】不定期連載「ニッポンの闘争遺産」長崎県川棚町川原「ダム小屋」
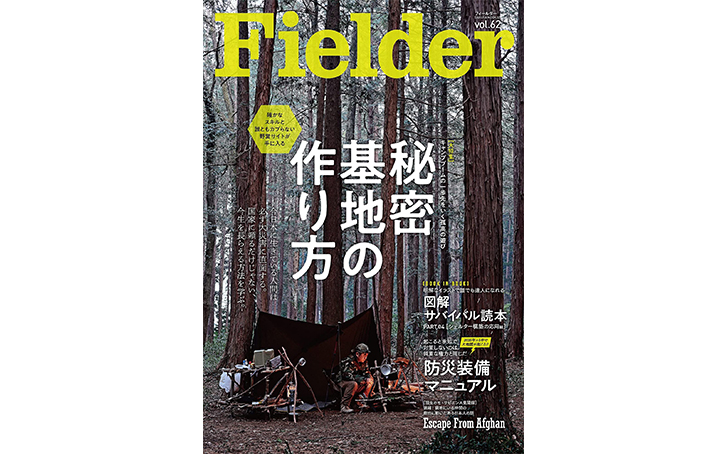

Fielder【Vol.62】新連載「山の謎なんでも探偵団」第1回「カッパは生きているのか?」
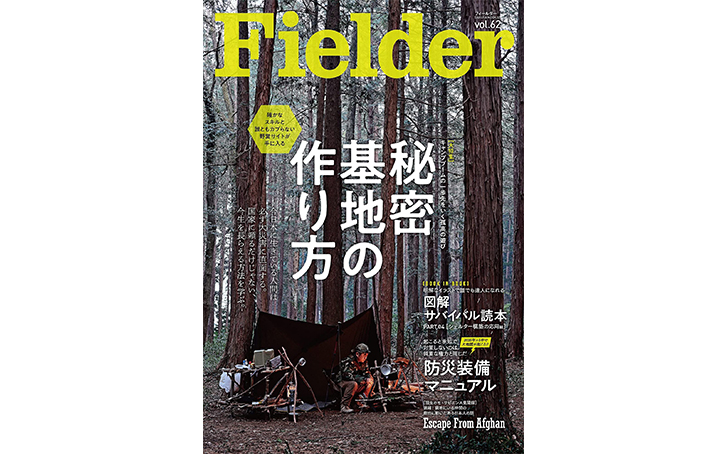
Fielder【Vol.61】「絶滅」野生動物生息記―スクープ編 イヌに最も違いオオカミはニホンオオカミだった!

家族は誰のためのもの?
共同親権への周知の広がり
共同親権訴訟、2月17日の第7回口頭弁論に先立ち、原告と仲間たちで毎回、家庭裁判所に申し入れた後、地方裁判所前で街頭宣伝をする。東京家裁では前回から、1階受付で所長に面談を申し入れると、総務課長と管財課長が降りてきて要望書を受け取り、その場で意見交換している。課長たちの見解を求めても押し黙るのはこれまでと同様だけど、所長や裁判官との意見交換を求めつつ、「運用は不公正」「親子関係を維持するのに何度も家裁に来る現状は税金の無駄」と伝える。
この間、共同養育支援議連会長の柴山昌彦議員が2月3日の議連総会終了後、報道陣への説明で、「一方の親の子どもの連れ去りについて、これまで『法に基づき処理』の一辺倒だった警察庁が『正当な理由のない限り未成年者略取罪に当たる』と明言し、それを現場に徹底すると答えた」という(牧野佐知子2022.02.05)。
その後、2月10日のネットでの討論番組(ABEMA
TV)で、議連の梅村みずほ議員と共同親権反対の論客、NPOフローレンス代表の駒崎弘樹が「連れ去り」をめぐって議論。ひろゆき氏(2チャンネル創設者)や北村晴男弁護士が動画で実子誘拐や共同親権に触れ、キリスト教会のサイトで親子引き離し問題への取り組みが語られるなど、当事者以外の人が共同親権について発言する機会が増えてきた。
「知られれば賛成が増える」
一方、裁判所前でのチラシ配りでは、同じ時間帯にチラシを配っていた団体の方から「共同親権って何ですか?」と聞かれている。世論の関心が徐々に高まる一方で、まだまだ行き届かない層が存在する。内閣府の世論調査(2021年10~11月)では、離婚後の単独親権制度については89・4%が「知っている」と答え、「知らない」の9・3%を大きく上回った。
調査では、離婚した父母の双方が未成年の子の養育に関わることが、子にとって望ましいかの質問に、「どのような場合でも望ましい」が11・1%、「望ましい場合が多い」が38・8%で、全体の半数を占めた。「特定の条件がある場合には望ましい」(41・6%)も含めると9割を超えた。この結果から、「知られれば賛否が割れる」ではなく、「知られれば賛成が増える」ことが予想できる。当事者が声を上げ続けることは、世論を作るにおいて必要最低限の条件だ。
国のための家族? 個人の幸せのための家族?
訴訟では、裁判所が積極介入する形で論戦が続く。現行民法の不平等を訴える原告に対し、裁判所は何と何が差別なのかと特定を求めた。原告側は民法818条3項の「父母の婚姻中は」共同親権とする規定(つまり婚姻外は単独親権でなければならない)が、法律婚とそれ以外の親子関係を差別するものである(つまり法律婚でしか共同親権が認められない)と主張している。
これは、親権のあるなしでの不公平の主張とは意味合いが違う。子どもが両親から生まれる以上、親子関係の固有性は、結婚という枠組みに本来収まらない。親権がないのが不公平だとすると、国が認めることで生じるにすぎない権利となり、天賦人権とは言い難い。それは、離婚はOKで未婚はダメとか、二級市民間で目くそ鼻くそ的に罵りあうことにもつながる。逆に、国が認めなければ親子関係が法的な保障されないこととなれば、国に適合的な家族の形を「正社員」になるために整えなければならないということになる。
単独親権制度ベースに共同親権を婚姻中にだけ一部適用しているというのが現状だ。その正社員の証として同じ姓の戸籍に所属でき、共同親権が特権的に形式上与えられる。この単独親権制度=家父長制が維持され、国が求める家族の形を整えるために、親たちもまた、世間から後ろ指刺されないように子どもを鋳型にはめ続ける。共同親権運動は、国のための家族制度、親権制度から、個人が幸せになるための手段として家族を位置づけなおす。
国の法制審の迷走、草刈り場となる子どもの意思
この間、国の法制審議会家族法制部会の議論を、「手づくり民法・法制審議会」で追っている。国の法制審は離婚時の子どもの養育について、テーマごとに議論を進めている。ところが、誰が子どもを見るべきか、共同親権についての共通認識を確立できないままの議論は、それぞれが見ている現場の現実から、事務局が出す論点に意見を出し合うだけ。かみ合いもしないし深まりもしない。税金の無駄である。国が設置を決めた子ども家庭庁についてのネーミングをめぐる迷走や、子ども基本法についての議論が低調なのも、子どもの養育の責任は第一義的には親にあるという当然の前提が、この国では共通見解にすらなっていないということの表れでもある。
子どもの意思を家事手続きの中でどのように反映させるのかの議論は法制審議会の中でも錯綜している。子どもの発言に大人と同様の結果責任をとらせることが、単なる親の責任逃れの過酷な行為であることを、民法学者の水野紀子は主張したりする。しかしその当の本人が、子どもが「自由に」意見表明できるための基盤を損ない子どもに親を選ばせる、単独親権制度の強力なイデオローグでもある。子どもの権利条約11条による、子どもの意見表明権は、子どもが自由に欲求を表明するための環境を整える大人の側の義務でもある。男性排除の「女性の権利」は子どもの権利に優先するという点では、彼女の差別思想は一貫している。それは古臭い性役割の焼き直し、「子育ては女の仕事」の言い換えにほかならない。
ぼくたちの訴訟は「親の権利(養育権)訴訟」だ。次回は国からの反論が予定される。現在裁判官へのハガキ送付作戦を開始した。国に対して義務を果たさせろという親の願いは、子どもの親として成長する喜び、つまり権利だ。それを損なってきたのが、単独親権制度にほかならない。民法に規定された親子関係しか保護されない単独親権制度がある限り、すべての親の権利は保障されない。親に口ごたえするのも親子喧嘩も双方の権利だ。ぼくたちは、単独親権制度の前にかき消されてきた、個人の尊厳と男女平等の回復を訴えている。
(2022.2.20 共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会冒頭コラム)
山と渓谷「北アルプス南部地域 登山道整備のこれから」
槍穂高地域で昨年行われた寄付金の実証実験について記事にしました。

「残念な県政」の継続か、「ワクワク長崎」を作れるか
2月3日に告示された長崎県知事選挙では、4選を目指す現職の中村法道氏(71)氏と大石賢吾氏(39)が出馬し保守が分裂した。これに対し、石木ダム建設反対を掲げた無所属新人の宮沢由彦氏(54)も立候補を届け出た。告示前の候補者討論会でも、石木ダムの建設問題が取り上げられ、選挙戦の大きな争点の一つになっている。
一昨年から長崎県内川棚町で建設が進む県営石木ダムの是非について、地元の川原地区を取材してきた。この地区は現在13戸50人が暮らしている。なのに、県が強制収用手続きを進めて、住民の土地を取り上げてしまっている。
「残念な県政」
長崎県に滞在しながらテレビを見ていると、長崎県では、石木ダムのほかに、新幹線の長崎ルートの建設のために佐賀県との折り合いがつかないというニュースが連日流れてきていた時期がある。新幹線が来てほしい長崎県と、通り道になるだけの佐賀県とは利害が一致せず、路線の末端の長崎県が先に県内の建設を進め、中間の佐賀県に建設を迫っていた。そうまでして作りたいなら、佐賀県は「いらない」と言っているんだから、長崎県が佐賀県内での建設資金を肩代わりするのが筋だと、長野県民のぼくは思う。しかし、理解しない佐賀県が悪い、という姿勢だと佐賀県の態度は普通硬化する。
テレビを見ながら、石木ダムと同じ構図だなと思った。この県営ダム建設は60年前に浮上したものだが、当初機動隊を導入しての長崎県の強制測量の強行に対し、住民たちは現地で実力阻止。対立の末に、工事の実施は地元の同意を得て行うという覚書を、県と地元自治会、川棚町は、1972年に結んでいる。
ところが、まだ13戸50人が住んでいるのに、中村長崎県政は 合意を無視して強制収用手続きを進めた。強制収用というのは、最後の1、2軒を対象とするのが通常だ。住民が立ち退かなければ意味がないからだ。強制収用史というものがあるなら、それこそ筆頭に上がるほどの、前代未聞の出来事だ。
今回、現地川原では、95歳になる松本マツさんにお話を聞いた。マツさんは、「こげんよかとこ住み着いてねえ、どこさ出ていくね」と口にしていた。

これまで住民が暮らしながらそのまま強制代執行がかけられたのは、成田空港建設のために、三里塚の大木よねさん宅が抜き打ちで取り壊された事例が、戦後はある程度だろう。よねさんは、空港公団が用意した代替住宅の入居を拒み、反対同盟が用意した仮の住処に移り住んでいる。
中村県政は、強制代執行をかけ、どこかの県営住宅にでも住民たちを放り込むつもりだったのだろうか。脅せば屈する、という程度のあまりにもの見通しの甘さに、住民の立場で見れば、今回出馬した宮沢氏のように義憤にかられるし、長崎県民の立場で考えれば、テレビで見る新幹線と同様、「残念」という思いが湧いてくる。
自民党県連が推す大石氏も、知事になれば建設を前提に話し合いをするというものの、それならばまず住民の意向を聞きに告示前に足を運ぶのが順番だ。当選したからとのこのこ顔を出したところで、県政に裏切られ続けた住民が「はいわかりました」というとは思えない。
宮沢氏は選挙初日に川原地区に出向いたようだが、今回、この中村、大石両候補が川原現地に足を運ぶかどうかは、選挙戦の注目点の一つだ。
どうやって「ワクワク」する?
長崎県は、本体工事の着工を表明して着手をニュースにしようとするため、抜き打ち的に橋をかけたりしたようなので、住民側の座り込み場所も以前より増えていた。1月に寒い中、火を囲みながら座り込んでいる住民の輪の中にいっしょにいると、まるで夜盗の襲撃に備える中世の農村にいるかのような錯覚を起こす。
ちがっているのは、相手が、自分が税金を納めている長崎県で、村の外からやってくるのが県の職員だったり、相手の武器が監視カメラだったりすることだ。
連日取付道路の建設現場で座り込む住民たちの苦労は並大抵のものではない。いつ工事が進むかわからず、県の職員と対峙しながらどこにもでかけることもできない。
一方で、それ以外の暮らしぶりは、地区内に反対看板はあちこちあるものの、他の周辺地域と何ら変わることはない。むしろ川棚町の中心部まで車で10分と立地的にも暮らしやすい地域の一つだというのもわかる。石木川の水も少ないので、佐世保に送るためにわざわざダムをつくる必要があるのかと見て思う。この辺のダム建設の合理性のなさを宮沢氏は訴えている。

「こげんよかとこ住み着いてねえ」というマツさんの口ぶりは、けして強がりではないと思える。60年間ダムの建設予定地とされ続けたため、行政によるインフラ整備は遅れ、その結果、タイムカプセルように他の地域では失われた村落周辺の自然環境が維持されている。ダム建設に対峙するという必要性があったとはいえ、助け合い、話し合いを重ねながら村の課題に対処していく住民たちに、村の民主主義のあり方を見ることもできる。
不幸な対立の結果とはいえ、川原地区が培った60年間の歴史と地域づくりは、むしろ長崎県がほこる財産に思える。これらすべてを水に沈めることは、むしろ長崎県の大きな損失だ。
この地域でいったい何が営まれてきたかを広く共有し、生かすべきところを生かしていくことは、カジノや大型開発に依存する県政運営よりも、これからの時代にマッチし、「ワクワク」する挑戦なのかもしれない。ほかのどこの県でもなく、長崎県だからそできることだ。有権者の判断に期待している。(2022.2.4)

2月20日投票、長崎県知事選挙で石木ダム建設問題が争点に浮上
保守分裂
2月3日告示、2月20日投票の長崎県知事選挙では、現在無所属5人が立候補を表明している。これまで3期にわたって知事を務めた現職の中村法道氏(71)の出馬に対し、元厚生労働省技官の大石賢吾氏(39)も立候補を表明して保守が分裂した。
これに対し、千葉県から宮沢由彦氏(食品コンサルティング会社代表、54)が石木ダム建設に反対を表明し出馬。田中隆治氏(78)、寺田浩彦氏(60)の新人2氏も立候補を表明している。
今回の知事選で、佐世保市のハウステンボスでのIR誘致、諫早湾の潮受け堤防の開門問題、長崎新幹線の建設をめぐる佐賀県との対立などと並んで、争点として大きくなりつつあるのが川棚町の石木ダム建設問題だ。
石木ダムは、川棚町を流れる川棚川の支流石木川に計画中の総貯水量548万トン(東京ドーム4.4杯分)、総事業費538億円の多目的ダム。県営ダムとして1962年に計画が浮上した。
建設予定地の川原地区には、13世帯50人が現在も暮らしダム建設に反対し続けている。過去には機動隊を導入した強制測量に対し住民が実力で阻止したこともあった。2010年には付け替え道路の工事着手に対し、住民たちが現地で阻止。2019年には長崎県が13戸の住民の土地を強制収用。現在も建設中の付け替え道路予定地での座り込みが毎日続く。

石木ダム建設をめぐってつばぜり合いの討論会
3日の告示を前に、1月30日に開催されたオンラインでの討論会「みんなで政策かたらナイト」(https://www.youtube.com/watch?v=LdsyZDxYNAE、長崎みんな総研が開催)では、現職の中村氏が、石木ダム建設反対の宮沢氏に対し、「長大河川のない長崎県では水の確保に苦労し一時長崎砂漠と呼ばれた。どうやって水を確保したらいいか」と口火を切った。
宮沢氏は「佐世保市の描く需要曲線は右肩上がりを描いている。これは人口が減っている佐世保市で本当に必要か。もともと針生工業団地建設計画のために作られた石木ダム建設計画ですが、その工業団地計画が破綻して、水の需要が減っている――」と回答。針生工業団地は現在、テーマパークのハウステンボスとなっている。「――例えば佐世保のサウナ、水をたくさん使うと思いますがこの30年水に対して危機感を持ったことがないというお話を聞いている。今の水需要の計画は非常に過大。それより、水が1日に6000トン、7000トンも漏れているのを直していったほうがいい」(宮沢氏)と答える一幕があった。
一方宮沢氏は、「石木ダムの問題は長崎県を前に進めていくためにはのどに引っかかった骨。取り除かないとどんな県政の課題も前に進めない」と主張。「中村さんの出身地の島原市では法道さんはいい人と一様に言う。一方で石木ダムで座り込んでいる人たちがかわいそうだという話も聞く。どうしてその法道さんが将来に禍根を残す強制収用をしてしまったのか。また収容の後に強制代執行をしなかったのか。思いとどまったお気持ちを聞きたい」と、中村氏の在職中の強制代執行について、あらためて姿勢を問うた。
これに対し中村氏は「住民生活の中で水の確保は非常に重要。他に安定的な水源がないような状況で石木ダムは必要不可欠。川棚川の治水機能を維持するためにも、この事業は進めていかなければならない。これまで半世紀近くの時間が経過しまして、歴代の知事も一生懸命取り組んできましたができれば私も地域の皆様のご理解をいただいた上で円満に事業が進められればと願っています。今後ともそういった方向で努力していきたい」と直接の回答を避けた。
長崎県は地元の理解を経て工事を進めるとの1972年の地元との合意を無視して手続きを進めた。また、長崎県との話し合いのために、現在進んでいる建設工事の中断を求めた地元の住民の要望に対し、中村氏は12年間の在職中応じていない。
候補者は石木ダム問題を解決できるか?
宮沢氏は「私が今回出馬のきっけかになった石木ダムでも、(地元の住民が)12年間も座り込みを続けている。これを放置して何が次の長崎の未来を作っていけるのか」とさらに言及。大石氏にも「こじれた石木ダムの問題をどう解決するのか」と水を向けた。
大石氏は「私も治水、利水の観点から(石木ダムは)必要。そういう意味では県政と同じ姿勢。まずはお話をさせていただきたい。宮沢さんも足を運ばれておられましたけども、私自身も足を運んでお話をして意思疎通をしたうえで理解を得たうえで実現したいと思っています。私がリーダーになりましたらそこをしっかりやっていきたい」
立候補を表明し川原地区を訪問した宮沢氏に対し、大石氏は中村氏同様、立候補を表明してから今日に至るまで、現地に足を運んでいない。
地元の住民とともに石木ダム問題に取り組む、石木川守り隊が実施した知事選立候補予定)者へのアンケート(http://ishikigawa.jp/blog/cat15/7939/)では、中村氏が記述で回答を寄せたものの、アンケートの設問には回答せず、大石氏と寺田氏は回答自体がなかった。宮沢氏と田中氏は設問の強制代執行に反対している。
筆者が1月18日から21日まで川原地区を取材した際、川原地区の住民と支援者は、付け替え道路の建設予定地で交代で座り込みを続けていた。筆者は2020年の10月にも取材で現地を訪問したが、住民たちはその時点で10年以上現地での行動を続けている。1年後の今回の訪問でも、同じ場所で座り込みを続けていた。本体工事の建設も見据えて座り込みの場所も増えている。

それ自体がニュースではないだろか。(2022.1.31)
ガサガサしてみる
大学の資料室から問い合わせがあって、『南アルプスの未来にリニアはいらない』を取り寄せたいという。大学の先生から購入依頼があったようだ。自費出版で出版社が倒産したので直接問い合わせが来る。あと5冊くらいしか手元にない。最近は死亡事故も起きて注目され、リニア関連の新刊も何冊か出ている。
ぼくが大鹿村を取材で訪問したのが2012年。今年で10年目になる。出版を目指して原稿を書いてお蔵入りもあった。派手な反対運動もなく小頓挫は表に出ない。リニアに関心がある人も少なかった。おまけにぼくも有名じゃない。
現地ルポは、ほかには樫田秀樹さんの本くらいしかない。研究者が調べものをするときに、参考にするということなのかもしれない。
あまり売れない代わりにマニアには受けるのか、ニホンオオカミの本は、理系の大学の国語の入試問題になったことはある。そういえば、最初に出した立川反戦ビラの本は、出版当時は本を読んだ方から100万円が救援会に寄付されたというのもあった(ぼくの懐は変わらなかった)。もう20年も前の本だけど昨年はアメリカの研究者から写真の使用について問い合わせがあった。この本も出版社が倒産している。
うちの父親は小学校の先生をしていて、若いころは山村の小さな学校に赴任することが多く、そのうち2校は生徒数の減少で閉校している。疫病神とは言わないけど、本を出してもらった出版社もぼくは2社が倒産している。「子どもは親の言うことは聞かないけど、親のするようにする」という。
親が学校の先生をしていてよかったなと思ったことの一つは、学校の先生も間違えるし知らないことも多いということに早く気付いたことだ。わからないことを父親に聞いて答えられなかったことがあった。「学校の先生なのに」と悪態をつくと「学校の先生だって知らんことはある」と父は答えていた。
そんなわけで、娘と2か月に1度会っていたときに、学校の話題が出たときには、「先生だって間違うことあるよ」「学校で教えることなんて目安だよ、目安」と教えておいた。娘は「目安って何」といぶかし気に聞いてきた。
「だいたいのところってこと。学校で教えているから正しいってことじゃない」
経験の中でそのうち意味がわかるかもしれない。すくすくと育った娘は、親に反抗して会いに来ず、裁判所が用意した茶番の子ども代理人に、父親への悪態をしっかりついていた。
リニアのことを書いたところで、出版までたどり着くのが遠そうなので、昨年末にカワウソと共同親権の本を二冊出版した。カワウソは高知でテレビ番組になったりして本も出ているようだ。高知市の図書館では5冊入れたカワウソ本が全部貸し出し中になっているという。一方、長野県内の本屋で売っているのを見たことがない。長野県は教育県と呼ばれているけど教育は間違っている。
地方紙にしても、行政情報の垂れ流しの翼賛報道か、東京の識者のインタビュー記事だけのページ構成と極端だ。たまにリニアのことでコメントを求められることもある。紙面を見るとどう見ても長野県には珍しい「活動家枠」扱いになっている。自分のことを活動家と呼ぶ人もいるけど、ぼくに言わせれば活動家というのは、動きが多くてガサガサしている人のことしかイメージできない。間違ってないかも。
あと最近、プロ市民とか呼ばれることもある。政治は市民がするものだ。ぼくに言わせれば、金もらって政治活動しているのは政治家なんだから、こういう呼称は民衆の政治活動を「特別なことと」思わせる呼称だろうなと思う。
そういえば、南アルプス本も、大鹿村の郷土文化館からJR東海の室長の指示で教育長が撤去させた。毎日一社ずつ新聞に電話して教育長に電話させたけど、あのときは新聞記者も「たいへんなことですよね」と言いつつ、記事にはしてくれなかった。リニア関連の市民団体に声明を出してほしいとお願いしてもどこも応じてくれなかった。
表現の自由を特別な人のものとする感覚が、自分たちの表現の幅を狭めていく。というか、言論弾圧なんて大げさ、小さな村の出来事でしょう、という態度の長野県の新聞記者や編集者もいて、その感覚はJR東海や村役場と変わらない。愚痴ったところで生活は豊かにならないので「大鹿村公認禁書」として箔をつけて宣伝しやっと完売。
最近はインターネットで個人が発信するのも簡単になった。ぼくもカワウソ本と共同親権本を売るために、ツイッターを始めた。大鹿村を「悪政のふるさと大鹿村」「日本でもっとも美しくない村役場」として絶賛売り出し中。大鹿村は人口が1000人を切った。人が出ていくのはいたくない村の環境だからだと役場の人は気づいていない。
同じ南信州で椋鳩十の出身地の喬木村は、「椋文学の里」で売り出している。ぼくもいっぱい本を出して大鹿村を「反権力文学の里」で売り出そう。宗良親王とかななおさかきとか、先人には事欠かない。大鹿に移住するとその日から悪政とたたかえる特典付き。
共同親権本のほうは、原稿料じゃなくて現物支給だったし、メディアでの宣伝も期待できないので、がんばって自分で売る。リニアには反対してくれる、共産党や社民党、週刊金曜日も絶賛共同親権にも反対してくれる。リニアのことでは勇ましい共産党の本村伸子事務所にこの件で連絡すると、面談を拒否される。彼らの中には昔は「北朝鮮が拉致するなんてありえない」と言っていた人もいただろう。
国際的には日本は実子誘拐の拉致国家だと批判の嵐になっている。子どもに顔を見せたいだけの親が外圧を期待して国際社会に訴えている姿は、外から見ると滑稽だろう。
カワウソの取材の中でキャッチした河童のことを聞くために延岡に行く。彼の地ではひょーひょーという声で山を登っていくことからひょうすぼと呼ばれる。それはホイッスルのような声を出すカワウソのことではないのですか、と聞くと、「あんた河童を知らんのな」といかにも世間知らずのように馬鹿にされるのだ。
お年寄り3人に集まってもらって話を聞く。「対馬でもおじいさんが河童と相撲を取ったという方に出会いました」と言うと、「それはあるだろう」という顔で見返されるのだった。案内してくれた地元の郵便局の橋本多都也さんは、夜釣りでドボンドボンと何十発と石を水に投げ込んだような音を聞いていて、そうするとカワウソとも説明しにくい。
橋本さんに聞くと「比叡山の千日回峰行の修行をテレビで見ましたが、山の中での暮らしは感性も研ぎ澄まされるので、私たちには見えないものも見えるということかもしれません」という。そうすると、そういった話を迷信や科学的じゃないと馬鹿にすることこそが、無知蒙昧な気がしてきた。自分で知った範囲のことでしか物事を考えずに、それを他人に押し付けることを科学の進歩と呼んで、夢のリニアは進むようだ。
帰りに実家の大分県犬飼町の書店「書林」に本を置かせてもらえないかと頼みに行く。
「いいよ。奥付に大分出身ち書いちょるな。ポップもいっしょに送っちょくれ」
店長は姉の同級生で、都会の書店で修業して戻ってきた直後は書籍も多かった。今は、昔はなかったパソコン教室の面積が増え、白髪の増えたおばちゃんの化粧品売り場はこじんまりと続き、最近は本は雑誌がメインで遠慮がちだ。なのにオオカミ本もいっしょに置いてくれるという。
大鹿では効かないつぶしだなとは思いつつも、大分に帰ったら帰ったで、大鹿のような目に遭う未来が見えないでもない。大分では「ガサゴ」と呼ばれていた。ガサガサして落ち着かない子どもはそう呼ばれる。
大鹿に帰ると水道管は止めていたのに、蛇口が1つと風呂の薪をくべる釜が凍結で壊れていた。隣の豊丘村も含め、死傷事故を起こしたJR東海は、豊丘村での工事を再開するという。やれやれと思って、「書林」に送る本を荷造りする。
(「越路」 たらたらと読み切り166 、2022.1.28)
写真は馬を引きに来るカッパ除けの猿の手を掲げた馬屋
12月10日『共同親権』発売開始!
親子の引き離しの現実を共有する語りの建白書。
共同親権は離婚を経験した親子だけの問題ではない。夫婦別姓や婚外子、同性婚、養子縁組や虐待、相続についても、あらゆる家族の問題で共同親権をどうするかがテーマになる。
それは家族をめぐる個々人の希望がもはや一つではなく、そしてにもかかわらず多くの人が家族に希望を求めていることの裏返しだ。共同親権とともに変わる、社会と家族のあり方の今後を考えてみたい。