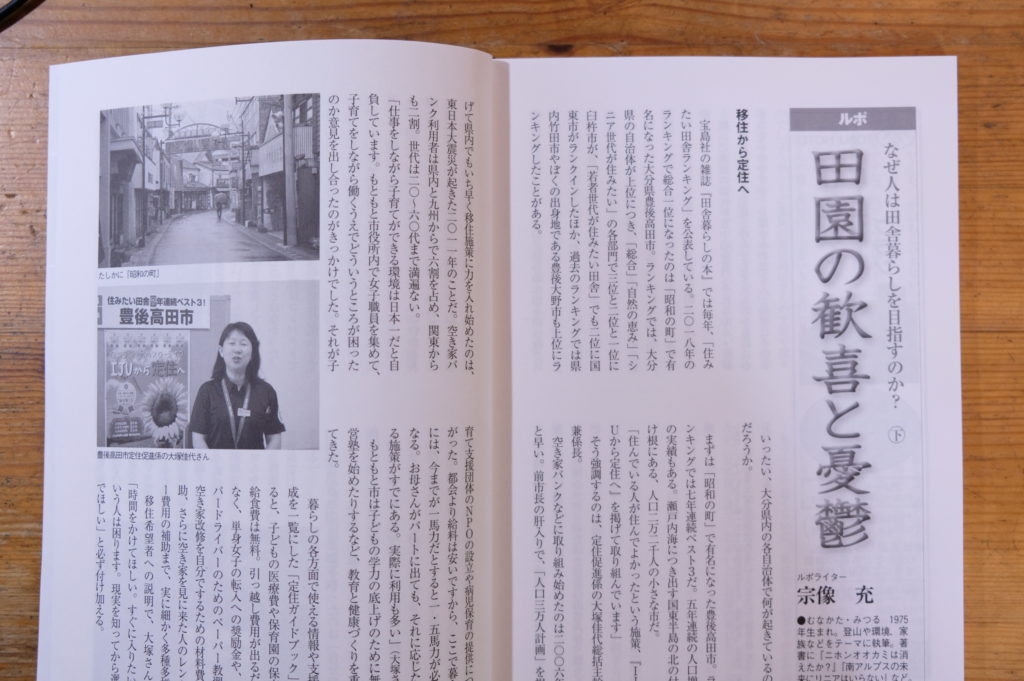「お子さんのお気持ちを考えてみてください」
今回は警察官が2人現れた。日曜日の午後2時に、千葉県習志野市の駅の交番の前で娘を待っていた。
元妻との間には中学3年生になる娘がいて、今14歳だ。彼女の連れ子の女の子もいて、今高3になっているはずだ。2007年に別れて、裁判所の決定が出た2010年から隔月や月に1回という頻度で子どもたちと定期的に会ってきた。上の子は中学校に上がるときに「会いたがらないから」と一方的に元妻に伝えられて引き離されていた。
下の子も中学校を卒業した段階で、行く予定だった公立の中学校に行っていないことがわかった。会ったときに本人に聞いても言わない。
この日は事前に母親側の弁護士から郵便で連絡があり、娘を待ち合わせ場所の交番前に行かせないと伝えてきていた。そうはいっても、実際に現地まで行ってみなければ、娘が本当に来るかどうかはわからない。
この間いっしょに付き添ってくれる友人2人と交番前で待っていたら、予定の時間に娘ではなく、元妻の再婚相手が現れた。
娘といっしょにすごす取り決めは午後2時~6時までだ。その間、娘はぼくに「うざい」「死んでしまえばいい」「お前なんか父親じゃない」とか悪態をついて、中途で帰ってしまう。追いかけるとけられたり殴られたりしたこともある。思春期の娘の反発としてはありうる範囲かもしれないし、「傷つくんだよ」と口で伝える。そうかと思えば、娘が生まれたときのことや昔いっしょに遊んだときのことを話すと、ボロボロと涙を流すことも度々ある。
一年ほど前に、元妻の再婚相手が、インフルエンザによるキャンセルを伝えてきた後、日程の調整という名目で連絡をよこし、結果会えなくなったことがある。
裁判所から注意をしてもらうと、再び娘がやってくるようになった。最近、元妻の夫が近くの銀行のロビーからぼくたちが会うのを監視していることがわかった。彼は元友人だけど、娘との直接のやり取りを邪魔するようになったので、別の友人に付き添ってもらっている。
この日付き添ってくれた一人は彼との共通の友人だ。しかし彼はぼくたちのほうではなく、交番に入っていった。娘を引き続き待っていたら交番から警察官が現れた。
彼のほうは、娘が書いたという手紙をぼくに手渡そうとしたけれど、娘から直接渡されるでなし、彼から受け取るものでもないので受け取りを拒否した。
娘が来ないなら来ないで娘の自宅に安否確認に訪問する予定だったし、以前もそうしたことがある。それを彼は嫌がって、何の容疑もないのに警察に相談し、彼の意向を受けた若い警察官が手控えるようにぼくを説得しようとして言ってきたのが冒頭の言葉だ。
「中学生の娘が男親に反発したりするのは普通ですよね。でもね、こうやっていろいろあっても父親が足を運んできているということは、今は意味がわからなくても、娘が大きくなって物事を客観的に見られるようになったときに、わかるようになるんじゃないでしょうか」
いつもこういう場面で答える説明をこの日もした。
その後、警察官たちは、ぼくを問題を起こす迷惑な存在としてではなく、娘の父親として見るようになった。もともと民事不介入で、警察官が間に入って交渉の仲介をする権限はない。「彼が問題を起こさない限りこちらにも付き添いもいるので問題は起きませんが、そんなに心配ならあなたがたが同伴して安否確認をすればいいでしょう」と言うと、「何かあったら所轄の署に連絡してください」と、交番前での足止めは終わった。
ぼくたちは友達の車で自宅訪問をし、インターホンを押して誰も出てこないことを確かめ、子どもたち2人への手紙をポストに投函して引き上げた。
日本では、親が別れた後に二人の親が子育てを継続するという発想は弱い。新しく家庭を持っているのに、別れた子どもと会うなんておかしいという発想は逆に強い。
子どもから見たら親は二人いるので、どちらかの親だけが子どもを見るというのは、親の都合を押し付けられていることになり、海外では共同親権という考えが生まれてきた。それを求めて国を訴える裁判を起こし、新聞記事になったりした。
「会えなくてもそのうち会いに来るよ」
と慰めなのか言われることはある。
だけど原告の中には、子どもが大人になっても会いにこないどころか大人になっても父親に住所を隠すケースもある。それでも子どもが気になるのか、彼は役所とやりあう。会いに来なければ親子の関係はそこで途絶える。別れた親どうしの関係が難しいのは普通だし、別れた相手の悪口を子どもに言って子どもが片親を拒否するようになるのは、ぼくたち親子でも同じで珍しくない。
制度で起きている片親の引き離しに国は責任を負わないし、当事者には何のケアもない。子どものことよりも、家や周囲の目を考えれば、そのほうが大人にとっては都合がいい。自分が子どもに会えなくて寂しいという思いはやがて薄れる。しかし、意図せず引き離され、子どもが捨てられているのではと悩む親は、自分を苦しめ続ける。
社会から疎外されがちな別居親という位置から人々を見ていると、コロナのもとでの人々のふるまいもよくわかる。
コロナの対策として外出規制が世界中で流行った時期がある。今も人の移動に対する人々の目は厳しい。そんな中、毎月ぼくは東京を通って千葉に出かけ、東京と長野の二つに分かれた別々の世界を見続けてきた。
欧米各国では、外出規制の例外として、国が別居親子の関係の継続指針を出している。子どもから見れば父母両方の家が自宅なのだから、外出規制は帰宅制限になる。国が帰宅を保護しなければ、親子関係という人権が、感染拡大を名目に損なわれてしまう。人々の移動が少なくなり、町に人がいない中での少人数の移動を感染予防と調和させることは、技術的にも難しくない。
ぼくも所属する別居親のグループも、アンケートで苦境を示し、同様の指針を国に何度も求めた。国はこれに正面から回答せず、オンラインでも面会を活用するようにとホームページに掲げた。子育てには、難しい思春期の子の対応やおむつを替えるなどもある。どこの世界にオンラインで子育てする親がいるのだろう。
それでなくても約束がなければ引き離されるのに、話のできない相手に一時的に取り止めを申し出れば、永遠の別れになることは目に見えている。会いに行く行かないは選べないし、子どもが親を選べないように、親も親であることをやめられない。
何しろ、子ども視点で考えれば、別居親に会うのが危険なら同居親と暮らすのはもっと危険だ。子ども視点で感染予防を突き詰めれば、子どもは施設に入れるしかない。しかし子どもはコロナにかかっても軽症ですむし、肺炎になって死ぬのはインフルエンザでも同じだ。
受ける影響は大きいので、コロナに関する情報を自分なりに検討してみた。
毎日テレビに感染者数が出てくるが、これは検査で陽性だった人の割合で間違いだ。コロナウィルスは移りやすいが、ほとんどは自然免疫で症状が出ないし、出ても軽症ですんでいる。現在の死者数は1万人を優に超えるインフルエンザの死者数の10分の1にも満たないから、恐ろしい疫病とは程遠いけど、マスコミはこういった比較を行わない。テレビは危機を煽ったほうが視聴率がとれる。コロナ以前、報道番組は低視聴率にあえいでいたが、コロナ特需で持ち直している。
PCR検査というのは、遺伝子を増幅させて読み取る検査の手法だ。増幅の回数で検出率は上がる。アメリカでこの検査の増幅回数を上げて「感染者数」を水増ししていた事実が明らかになっている。
すでにコロナウィルスへの暴露という観点からは、日本の状況は集団免疫に達しているというのを、免疫学者も言っているし、毎日のように、医学の観点からコロナ対策の無意味さやマスコミ批判をネットで続ける大学教授もいる。
そもそも感染者は次に似たようなウィルスが出てきたときに、免疫という観点からは人々の防波堤になる重要な役割を担う。だいたい元気な人はかかっても軽症ですむのだから、黙って家で寝て直したほうがいい。
感染者を社会から排除するのは、感染者を出し営業停止措置に対して保証したくない行政の都合にほかならない。本当にまともな対策をしたいなら、科学的な観点からのコロナの危険性(の少なさ)と過去の政策の無意味さをあらためて説明し、なおかつ感染によって偏見も含めて暮らしがままならなくなった人への生活保障を国がすれば偏見もなくなる。
先日、こういった視点を東京の別居親の仲間にしゃべってみた。
「こういうのはみんな世間では実のところ知られていることじゃないでしょうか」という。
国の政策の誤りや数値の操作を多くの人がうすうす気づいている。だから東京では、飲食店に客はいるし、電車もお年寄りの姿を見ることは少ないけれど、そこそこ人が乗っている。周囲で死者が次々出るような状況でもないのに、意義を感じない生活上の制約を受け入れ続けるのは難しい。
しかし別の視点を持った報道はテレビではなされない。自らが洗脳した視聴者の反発をテレビは恐れ、流す情報を統制し、コロナとの戦いを続けさせる。これが、効果がないとうすうすわかっていながら、マスクをみんな外せない理由だ。
社会に正気を取り戻し敗戦からの復興を急ぎたいなら、自らが「非国民」と名乗り出るしかない。
一人じゃない、別の見方もあると確認するために、同じ悩みを抱えるもともと疎外されてきた別居親たちの話しを聞き続けていたのは、お互いに孤立して闇夜に投げ出されることを防いでくれていたようだ。社会全体が周囲から自分がどう見られるかという視点だけを気にするように人々に仕向けている。
そんな中、それとは違う見方があると伝えられる存在があることは、子どもに限らず、多分貴重なことなのだろう。
(2020.9.18、越路18号、たらたらと読み切り158)