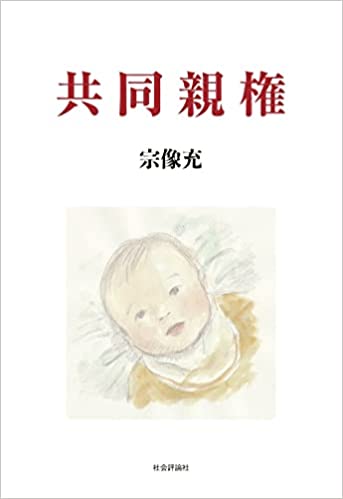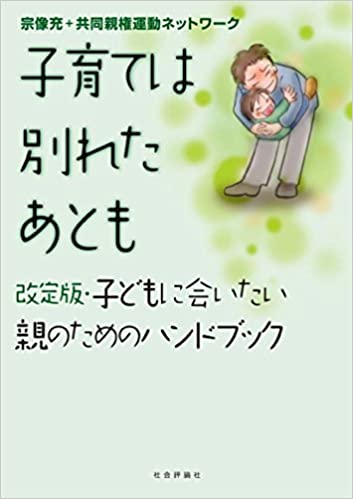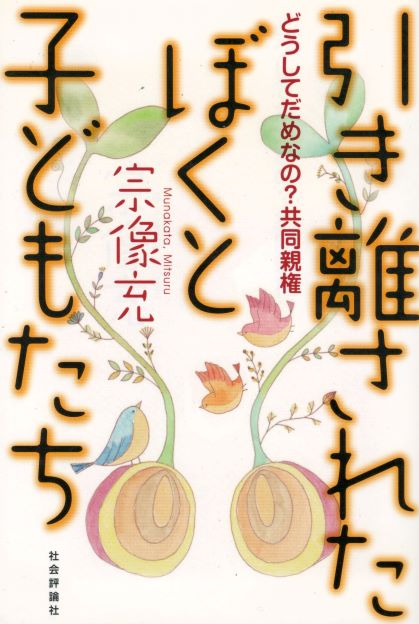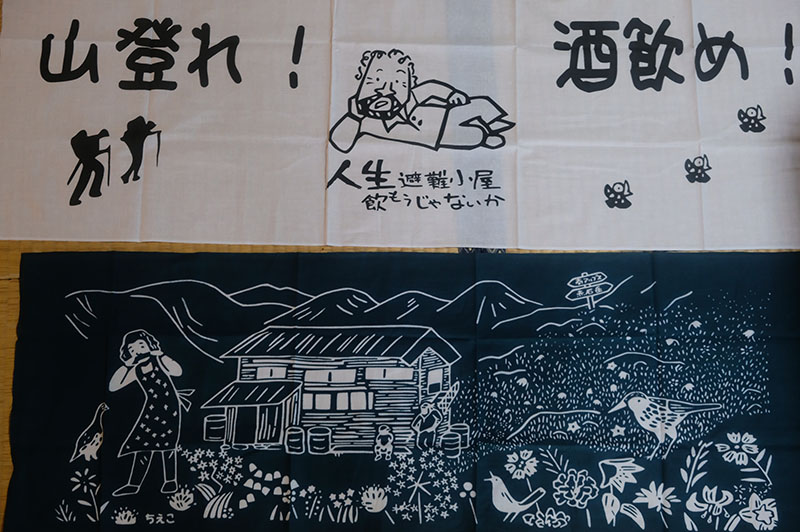宗像 充
1 子どもに会えない父親として
私は2007年に事実婚だったパートナーとの関係を解消し、その後親権がないがために人身保護請求を申請されて、今現在子どもと会えていない父親です。人身保護請求がされた際には、元妻側は会わせると自ら申し出たため、合意書を交わして任意で当時2歳になる前の子と、私が手元で育てていた元妻の連れ子の4歳子どもを渡しました。そのころ二人で子どもを協力してみるようにできるまで私の側が暫定的に2人を預かっていました。
ところが子どもを渡した途端に2年子どもと引き離され、調停や審判を経て2か月に1度2時間会えるようにはなりましたが、現在は「子どもの意思」を理由に会えなくなっています。
その間私は5度も裁判をしました。子どもとの関係を維持するためです。現在、単独親権制度の違憲性と、立法不作為を訴えて2019年に国を提訴した訴訟の原告です。果たして共同親権であったなら、このような苦労を15年間も私たちがし続けることがあったでしょうか。
私どもの主張は、「手づくり民法・法制審議会」の意見として述べています。私の経験も踏まえ、以下の各点を求め、私が強調したいこととその理由を述べたいと思います。
2 父母の権利(親権の用語変更について)
「親権」の呼称については現状のままでよい。親権は「子どもは父母と共に過ごし成長する権利を有する。子の養育及び教育は、父母固有の権利であり、その権利義務の総体を親権とする」(大鹿民法草案)と明文規定を置き、父母の権利の固有性を明示する。
(理由)私は一度も親権をもったことがありません。それを理由に人身保護請求をされました。しかし、定期的な面会交流の審判が裁判所から出ています。一方、元妻は子どもを確保した後、現在の夫と結婚し、子どもを養子に入れました。そのことによって親権者変更の申出はできなくなっています。私たち父子は制度の濫用によってこの15年間振り回され、今も振り回されています。
養子縁組は子どもの親を取り換える制度になっていますが、子どもとの面会交流はいったいどんな権利に基づいているのか、親権の概念を設定し直したところで、父母が、実父母または養父母になっているのであれば、意味のないことです。
父母のセックスによって子どもができるのですから、親権制度によって保障する父母の権利の固有性をまず規定しないと、いくら用語を変えても無責任というだけでなく、国や家の都合でいかようにも親の権限を取り上げることができます。私は子どもを手放すように何度も司法に無言で圧力をかけ続けられましたが、現行制度は無責任な男女のための制度になっています。
一方で、審判では、元妻の連れ子と私の面会交流を規定しています。父親替わりとして私と子どもとの関係を司法が認めたということですが、そもそも父子(親子)関係を保護すべき、という発想がなければ、それを延長して父子的関係を保護するという発想自体ができません。
3 共同親権(親権の偏在の解消)
現行民法の単独親権規定を削除する。父母の権利の対等性を規定するため親権の調整規定においては、父母一方の申出による養育計画を義務付け、養育時間の平等を基準に司法の裁量を制約する。監護権を親権からの分離はしない。
(理由)父母の権利を保障する法規定が親権である以上、それを片方に偏在させる理由がありません。共同親権は導入するものではなく、もともとのベースとして設計していないことに問題があります。ベースが共同親権ですから、婚姻中と離婚時だけでなく、未婚時を法的に区別する必要もありません。今回の中間試案は、現行制度を元に積み上げ加算方式で選択肢を設けたため、1で私が述べたようなベースとなる議論がなされず、結果議論を集約できなかった事務当局の(半分意図してした)失敗だと思います。したがって、中間試案の選択肢の中からどれかを選ぶという行為自体が不可能で、人気投票以外の意味はありません。
私は、親権はありませんでしたが、子どものことについては、授乳以外はまずしましたし、その時間も少なくありませんでした。しかし元妻は、全面的に私の収入に頼っておきながら、私の稼ぎが少なかったことを15年後の今も責め立て続けています。その上、今度は別の男性に子どもを見させて私が子どもに対して会おうとすると、裁判までして引き離そうとしています。司法は一貫して母親側の肩を持ってきましたが、子育ては女がするものという固定観念がなければ、考えるだけでもおそろしいことです。
性役割に基づいて、このように一方の親を子どもから排除することが可能なのは、単独親権規定があるからです。特に離婚時に親権を司法が母親に指定する割合は94%なのですから、単独親権規定は父親を育児から排除し、働く女性が子どもの面倒から離れられない事態を招いています。経済的にであれ、実際の子どもの世話の側面であれ、性役割に基づいて双方の権利や責任を振り分けることは、男女平等の側面から受け入れられないだけでなく、それを固定強化して、ジェンダーギャップから生じる父母の争いを温存させます。
共同親権を名目上入れて、監護権で今度は性役割を押し付ける現行運用を温存し続ければ、今の制度に対する不満も温存します。司法が公平な判断をできる法的根拠がないことが問題なのですから、司法の裁量の幅を狭め、養育時間において男女平等が実現する法規定を置いてください。(大鹿民法草案12ページ以下)
4 養子縁組(代諾養子縁組、未成年者の普通養子縁組の廃止)
再婚時の父母の同意と司法の関与を省略する代諾養子縁組制度、及び、片親を養育から排除するために濫用される未成年者の普通養子縁組制度を廃止する。
(理由)人身保護請求をされた後、元妻とその結婚相手が子どもをすぐに養子縁組して2年間も子どもから私を排除しました。私はそれまでひとりで子どもを見ていたので、正直、子どもを物のように扱ってよしとする法と司法のあり方に、本当に傷つけられました。子どもの養父となったのは、私の元友人でしたが、彼は、私と子どもとの面会交流を、近くの銀行のベンチに座って監視したり、元妻やその弁護士とともに「つきまとう」と父親である私に対して暴言を吐いたりしてきました。これらの行為を司法は「親権者だから」と容認しています。倫理が壊れています。
代諾養子縁組において、父母の同意と司法の関与が省略されたのは、そのことで子どもの利益を達成できるという前提があったからだと思いますが、養父が子どもの前で実父に「つきまとうな」ということにどんな子どもの利益があったのでしょうか。代諾養子縁組制度の濫用がなされるのは単独親権制度だからですが、これを廃止した場合に、代諾養子縁組制度は必然的に廃止され、さらには未成年者の普通養子縁組自体の利益自体がなくなります。そのような場合は、特別養子縁組をすればよいからです。
5 子どもの意思(子どもの意見表明権と自己決定権の混同)
父母の権利行使について、子どもの意見を考慮することを義務付けること、及び、司法の現在の運用を肯定するために「子どもの最善の利益」など曖昧な言葉を用いることをやめる。
(理由)私は、これまでの調停、審判で5度ほど子どもの意見聴取をされました。2度は同じ裁判で、子ども代理人が意見聴取し、その後調査官が再び意見聴取をしました。そのとき子ども代理人の役割は、家から裁判所に子どもと同行することでした。そしてすべての意見聴取において、私は親としていつどこで意見聴取がなされたか事前に知らされていません。子どもと試行面会で裁判所で会いましたが、元妻とその夫がマジックミラー越しに監視しました。屈辱で本当に傷つきましたが、調査官は「親権者ですから」と言っていました。
子どもは最初のころの聞き取りでは、面会交流について素直に喜んで調査官にもそう話しました。しかしそのことで面会交流の時間が増えることはほとんどなく、逆に、思春期になって子どもが会いたくないと言い出すと、裁判所は即座に自分が定めた面会交流の取り決めを取り消しました。こんないい加減な家裁の実情が表に出れば「子どもの最善の利益」が判断できるかなんて、信じられる人はいないと思います。中間報告では、父母の権利の固有性について沈黙してそれを確保する手段である親権の議論をしたために、政策判断や司法担当者の主観一つで、父母の権利をいかようにも制約することが可能になっています。「子どもの意見の尊重」の運用実態です。
裁判官はただの公務員ですから、自身の裁量が大きすぎれば前例以上のことはしにくいのは自明です。なので、司法での母親の親権者指定が94%となっていますし、これは子どもといっしょにいる時間の長い母親がもっぱら子どもを連れ去る結果ですが、であれば、一般の方の司法への信頼を保つためにも、もっぱら母親が親権者を得る、と明記すべきです。男女平等の観点からそれができなければ、男女平等に養育時間を分け合うように明記するしかなく、それをしたくないからといって「子どもの意見の尊重」を持ち出して、子どもに責任を押し付け、司法に都合のよい子どもの意見だけを尊重しない親を責めることを司法に許すなど、はしたないことです。
子どもの権利条約は「自由に」子どもが意見を表明する権利があることをその12条で明記していますが、未熟な子どもに自己決定を迫り、意見がまとまらない親の責任を肩代わりをさせ、無責任なだけでその後の子どもの人生など何も見届けようとしない司法のしりぬぐいをさせるなど、私たち大人はすべきではありません。