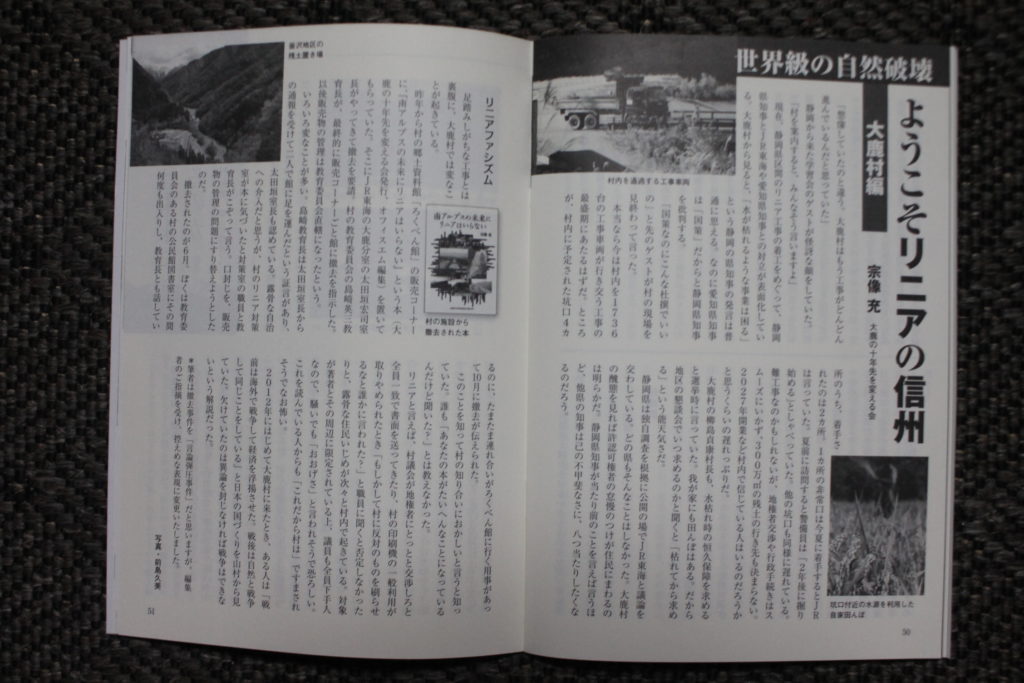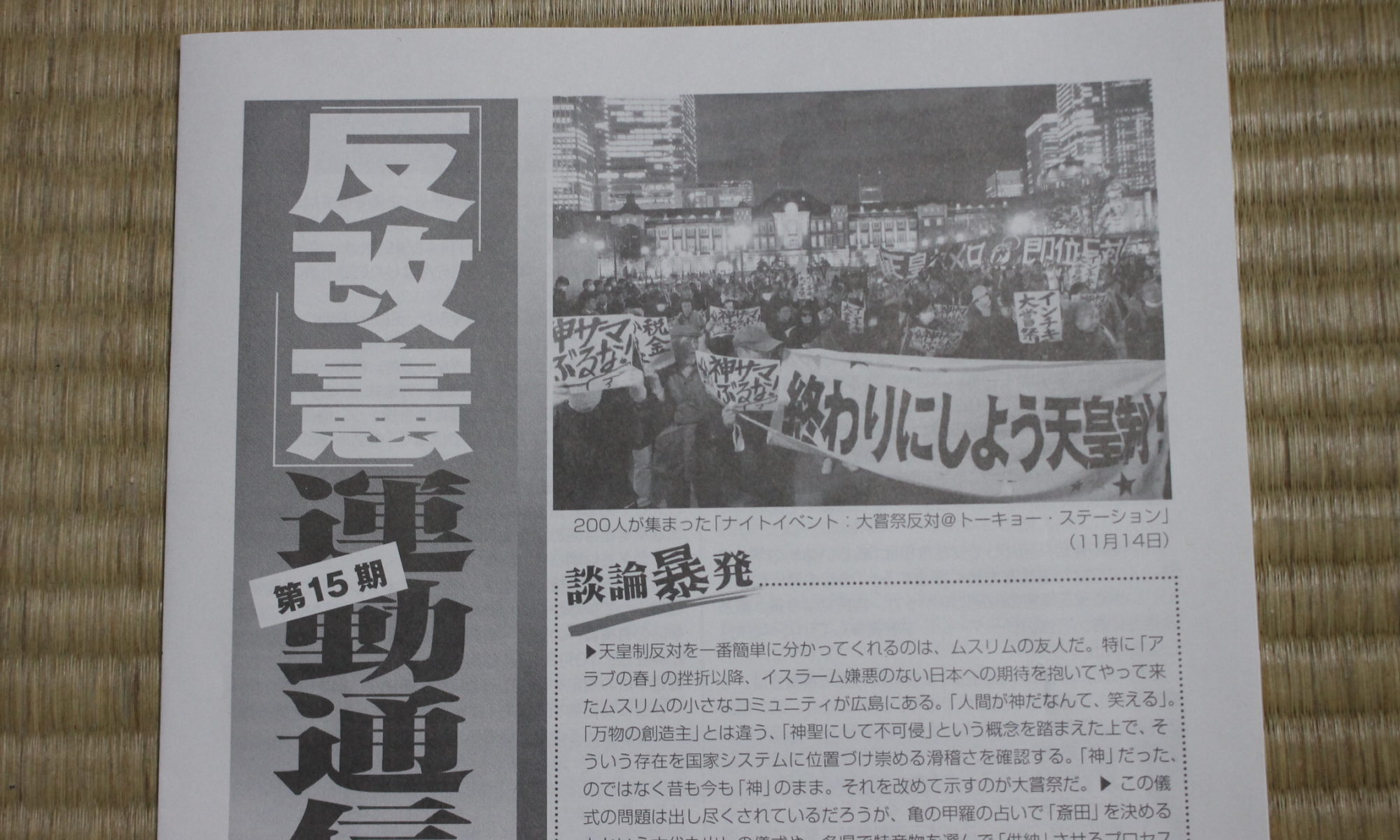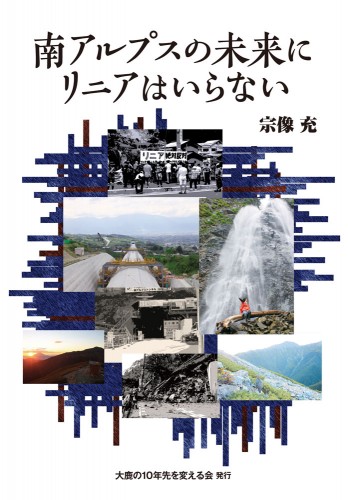ドアの外からピンポンすると住居侵入
「子どもたちが生きているか確認したかった。無事だと教えてほしいと何度もお願いした。なのにたった一回の回答もない。子どもたちは誘拐されている。悲しみしかない」
スポーツジャーナリストとして日本で活動していたオーストラリア出身のSさん(45歳)は、そう言って涙ぐんだ。
Sさんが義父母が暮らすマンションを訪問したのは、大型台風が関東地方に上陸し、多数の被害が出た昨年10月のこと。
「子どもたちが心配で、家庭裁判所にも警察にも妻の家族にも安全でいるのか安否確認したかった。無事だと教えてほしいとお願いした」
その日のことを1月10日の公判でSさんは振り返った。義父母のマンションを訪問した1月半後、11月30日にSさんは、自宅マンションで逮捕された。この日検察側は「関係者以外立入禁止」の掲示が出ているにもかかわらず、住民の後についてオートロック式のドアからマンションの共有廊下に立ち入ったことを「住居侵入」と主張。Sさんも容疑を認めたが、一方で度々「誘拐」という言葉を証言の中で口にしている。Sさんの妻が11歳の娘と8歳の息子を連れていなくなったのは昨年5月のことだ。以来子どもたちと会えていない。
国内外の法制度のギャップ
Sさんの母国のオーストラリアに限らず、共同親権の法制度が整えられてきた海外では、親による連れ去りも「誘拐」として刑事事件化される。しかし、日本ではここ2年ほど、誘拐罪での告訴が受理された事例が各地で見られるようになったものの、検察はただの一度も起訴したことはない。しかし、海外であれば拉致の実行犯が「被害者である」ことを主張すれば、「保護」を名目にした「支援」を行政が整える。一時的な保護施設の提供や住所の秘匿がなされ、何の説明もされずに親子がそのまま生き別れになることも少なくない。海外出身の親たちが、「拉致」と日本人以上に憤りを日本の制度に向ける理由だ。
法廷には、オーストラリア大使館の職員も傍聴に駆け付け、この裁判が、日豪両国の制度の違いから生じた「事件」であることを物語っていた。
「子どもに最後に会ってから238日 」
「これは私が撮ったものです。これは私の妻が娘と息子に対し叩くなどした虐待の写真です。これで妻の虐待の証拠が明らかになりました。感謝します。私は一度も子どもを虐待したことがありません」
妻側が出ていったのは、娘がSさんから暴力を振るわれたと妻に言ったことがきっかけだったと、検察側が妻側の行動を擁護するために持ち出した証拠に対するSさんの受け答えだ。
「誘拐があったから犯罪が正当化されるとか、刑が軽くなると考えていますか」
検察官とSさんとのやり取りを見ていた裁判官がそう問いかけるとSさんは否定し、「違法で正しいやり方ではないと理解している。そこは謝罪するが、離婚手続きとは別」と反論した。
Sさんは現在妻との間で離婚調停中で、子どもに会うために面会交流の調停中でもある。ただ「子どもに最後に会ってから238日が経過」している。ぼくは多くの別居親の相談を受けてきた。こういった手続きが少なからず空手形で、会える会えないは実際には同居親の意向次第だ。だからSさんも会えていないのは理解できる。
しかし、「今後は法にのっとって離婚手続きをするか」という検察官の質問に「はい」と答えなければSさんの保釈は叶わない。人質司法はカルロス・ゴーンが訴えた通りだ。法にのっとった手続きでは埒が明かないのでSさんは直接居所を知ろうとした。その手段を手放せというなら、「子どものことはあきらめろ」ということだ。
政治弾圧としての逮捕劇
司法や行政は、子どもとの関係の継続を願う親たちをあきらめさせるために、度々「別件逮捕」を繰り返してきた。子どもを連れ去られたから取り戻したことが誘拐罪にされ、服役した人もいる。ぼく自身も、決まっていた面会交流日に子どもが現れないので、子どもの家を訪問しようとして、まだたどり着いてもいないのに、警察を呼ばれたことがある。
ただ、子どもの暮らす家の敷地やドア内に入って、逮捕・勾留される事例は度々あるが、起訴されたのを聞いたのは今回が初めてだ。外国人で引き離された親たちは、国内外の制度の違いから、国内拉致を許す司法に批判的だし、実際、家に行くなどの直接的な手段をとる人もときどき聞く。それら「共同親権」の旗印のもと「一目会いたい」(Sさん)と願って行動する親たちへの見せしめとして、今回の起訴が行われた。
実際、住居侵入の保護法益は「住居の事実上の平穏」だ。ぼくは、自衛隊官舎へのイラク派兵反対のポスティングが住居侵入罪に問われた、立川反戦ビラ弾圧事件の救援にかかわったことがある(『街から反戦の声が消えるとき 立川反戦ビラ入れ弾圧事件』、2004年)。
そのとき、「ピザ屋のチラシも寿司屋のチラシも入っているのに何で反戦ビラだけがダメなんだ」という疑問とともに広範な救援運動が広がり、一審では「表現の自由」を明記した憲法に照らし無罪とされている(控訴審で一人10万の罰金刑。最高裁で確定)。その疑問への答えは、このときの逮捕・起訴が自衛隊のイラク派兵直前になされた運動つぶしの口封じの一環で、政治弾圧だったからだ。
Sさんは住民の後についてオートロック式のドアからマンションの共有廊下に立ち入って逮捕・起訴された。居所を聞いた両親に会えていないし、オートロックのドアの中の共有部分でも無許可でNHKの集金は入っている。そのうえ「子どもの安否確認」という正当な理由がSさんにはある。「誰かが私のアパートにやってきて、私の持ち物を全部持ち出した。鍵は妻と妻の母が持っていた。今、私の財産はスーツしかない」とSさんは嘆く。警察がSさんが勾留中であることをSさんの妻に教えたのか、住処を奪われたのはむしろSさんで、こうなると被害者はどっちだとしみじみ思う。
一月も勾留されたSさんは塀の外に出るために汚名をあえて着たが、親の養育権を憲法上の権利として掲げて闘えば、もっと粘れたのではないだろうか。
1月15日、Sさんに対し懲役6月執行猶予3年の判決が出た。検察の求刑通りの司法判断。
この事件もまた、海外からの批判で国内拉致司法の実態が覆い隠せなくなった中、共同親権の議論が国内でまきおころうとするときに行われた政治弾圧にほかならない。検察が海外同様拉致を問うていれば、起きようのなかった事件なのだ。