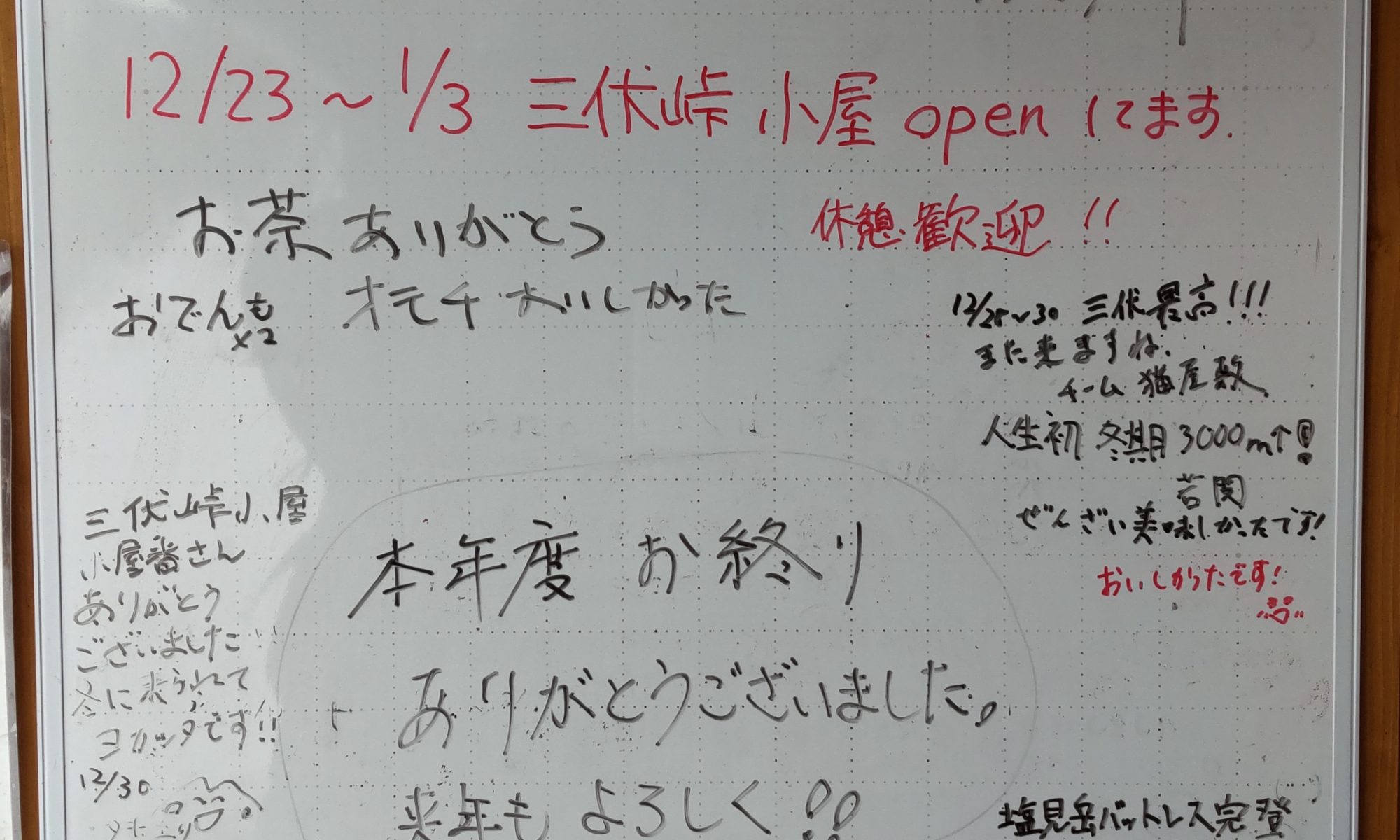左派系党派が共同親権反対を表明
4月16日に「離婚後の共同親権の導入」を盛り込んだ民法改正法案が衆議院を通過した。衆議院で法案に反対したのが確認できるのは、共産党、れいわ新選組になる。前後で左派系党派が反対をおっとり刀で表明している。みどりの党、生活者ネットなどだ。社民党は福島みずほや大椿ゆうこが反対集会で発言している。
中身を見てみると、DVが継続する、合意が得られない場合の混乱などがもっぱらで、かねてからこれらの批判は既得権にすぎないと批判してきた。海外では共同親権でも対策がとられるし、DVや虐待は年々認知件数は過去最高を記録し、単独親権制度にDVの抑止効果はない。それどころか、子の奪い合いや育児の孤立による事件はいくらでもあるからだ。
男性の側のDV被害も報道されるようになった。司法で女性が親権を得る割合は94%だから、親権者に多く加害者が含まれているのは明らかだからだ。これらは被害者保護や暴力抑止の失敗の末であり、共同親権を犯人に仕立て上げるのは無理がある。
共同親権は家父長制の復権は本当か?~家族主義的な反対論
共同親権反対には共同親権は家父長制の復権でバックラッシュだ、という根強い意見がある。
しかし、戦前は家父長制家制度のもと父親単独親権で、父母同権の共同親権を求めてきたのはもっぱら女性たちだった。
現行民法は日本国憲法が5月3日に施行された1947年に改正案がまとめられ、翌年から施行されている。今回と同じく法制審議会と法務省は関係団体に意見の照会をしている。
その際、当時の主要な女性の法律家や研究者、共産党や婦人民主クラブの活動家などからなる家族法民主化期成同盟会は、民法改正案における修正意見を出し、「氏」に実効的効力を求める規定の削除を求めた。そして、「婚姻、離婚、私生児認知などの場合に、子と氏を同じくする父母の一方のみが其の子に対し親権を有するのは不当であるから父母は親としての関係に基き常に子の監護、教育について権利・義務を有するものとすべきである。 」と父母による共同親権を求めている。
同盟会には法制審議会委員の川島武宜 もいて、戦前の家制度が「氏」によって夫婦と未婚の子の戸籍制度として温存されたその経緯を理解していたことがわかる。こういった意見は唐突なものではなく、戦前には実現しなかった民法改正の議論を踏まえたものだ。
男女同権や未婚の母の法的地位の確保という観点からは、共同親権を婚姻内にとどめる理由もない。実際、準備が間に合わずに憲法施行から翌年の現行民法の施行までの間に一時的に適用された「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」(応急措置法)では、婚姻内外問わず一律共同親権とされた。すべての子どもに親の保護を与えるのが狙いだったことを当時の裁判所は述べている。離婚や認知の場合の親権者は協議によって決めることも可能だった。実際共同親権で離婚したカップルもいた。
1948年から施行された民法は、共同親権を婚姻中のみにとどめ、たいした議論もないまま「氏」のもとに残った家制度と手打ちをしている。
「寅に翼」の時代~現代の女たちの勘違い
NHKの連ドラ「寅に翼」で戦前の女性たちが置かれた法的立場が注目されている(見てない)からか、共同親権の立法化が先行し、自民党の反対でとん挫した夫婦別姓が進まない女性たちのいらだちを、度々記事やネットで見かけることがある。しかし「寅に翼」の主人公「猪爪寅子」もまた、司法事務官和田嘉子としてこの期成同盟に名を連ね、共同親権を求めている。「ふぇみん」の赤石千衣子さんの婦人民主クラブや共産党の人も期成同盟にいる。
共同親権はバックラッシュだという女性たちの反発に、何を言っているんだろうと最初思った。女が親権をせっかくとれるようになったのに、また男(父親だけど)に口を出されるのかという心情は想像できる。実際、戦後初期は女が親権をとれない状況で、親権取得率の男女割合が逆転するのは1966年になる。
しかし、共同親権が父母同権を実現する手段であったなら、1966年後に男女ともに親権がとれるようになった時点で法改正をしておくべきだったのだ。しなかったのは、氏によって残存した家制度が法律婚優先主義の意識を定着させたので、「婚姻外の差別的取り扱い」に疑問を感じる感性が奪われたからだろう。歴史的経過を振り返れば、司法で女性が親権をとれる割合が94%になった時点で、共同親権に反対することは、いろいろ理由をつけようが既得権以外に説明のしようがない。
共同親権反対という改憲運動~男女同権の遺産を食いつぶしている
ところで、今次共同親権に反対論者や政治党派は、護憲を標榜する人が多い。自民党の改憲案が婚姻の自由と家族における個人の尊重と両性の本質的平等を規定した憲法24条の復古主義的な改正も視野に入れているので、その自民党が推進する共同親権法案について、警戒しているのはわかる。
実際、親権をもてない女性のための便宜であった監護権は共同親権であれば不要なものなのに、逆に共同親権時にも他方親を排除する権限として温存され、その点では危惧も根拠なしとしない(この点から単独親権制度の廃止を求めてきたぼくたちは法案には反対した)。
しかし、共同親権に反対する人たちが求めているのは、逆にこの監護権による事実上の母親単独親権の司法慣行の温存である。結果的に子を確保できる状況にない大部分の男と、女だけが子どもを見ることを潔しとしない少数の女が割を食う。
これでは戦前戦後と女たちが求め日本国憲法の施行によって実現した男女平等の成果を損なってしまう。自民党の狙い通りに家族の国家支配を強化し、改憲を促進するだけだろう。民法改正のこの時期に、護憲派が何をしたか、記憶に残すためにこのエッセイを記録に残すことにする。(2024.4.24)