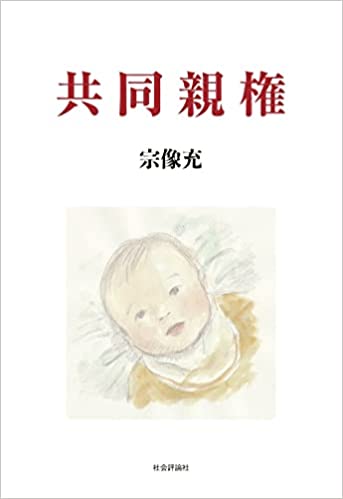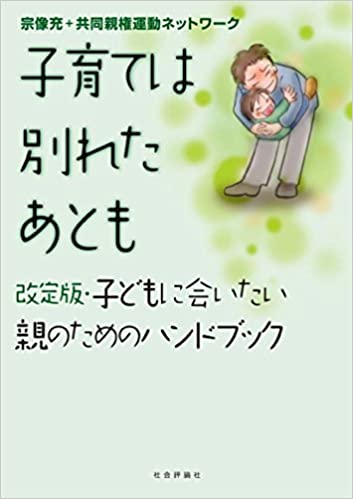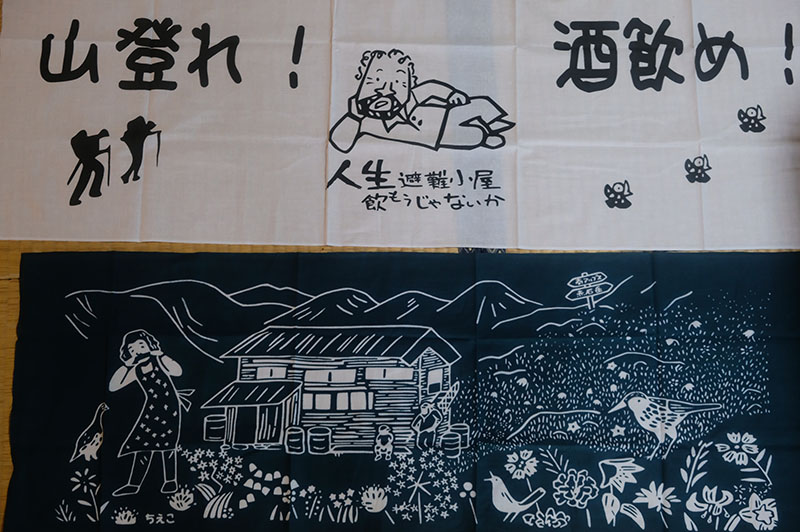一審は「差別的取り扱いは合理的」
6月22日の一審における不当判決から4カ月が経ち、共同親権訴訟は11月2日に控訴審の弁論が始まる。通常控訴審は1回で結審することも少なくないため、初回結審を阻止するために多くの方に参加傍聴をお願いする。
一審判決で古庄研裁判長、石原拓裁判官は非婚の父母の「差別的取り扱いは合理的」と原告の訴えを退けた。法制審議会で単独親権制度の現行制度を維持する選択肢が事実上排除されたと報道される中、この極端な反動ぶりは司法の感情的な反発と組織防衛の反映である。判決内容自体も矛盾をはらむ。原告側の議論の提示を否定するために先行判例を物色したものの、先行判決との論点の違いを司法が解消できなかった結果である。
結果、母親(父親)が孤立した子育てをするのも、婚姻外の子どもが親を知らないのも、制度の問題ではないと判示してしまった。これは婚外子差別に反対し、ひとり親の困窮をアピールする人たちにとっても、素直に喜べない結果だろう。
司法の逆コース
9月27日には、連れ去り国賠訴訟で東京高裁の不当判決が出ている。高裁はあえて「(現行の)家裁実務に対し、強い批判があることは窺われない」との文言を判決文に入れ込んだ。また、当裁判の原告の宗像が問うた面会交流不履行に対する損害賠償請求や、他の複数の面会交流不履行の損害賠償請求訴訟で、このところ高裁での棄却判決が出ている。以前は債務不履行として司法が判例を積み重ねてきたのにだ。
昨今の実子誘拐批判、連れ去り容認司法批判の中で、権利回復を求める被害者の訴えを逐一否定することによって、司法は権利主張そのものを抑え込もうと必死だ。しかしこれらは、司法決定自体を司法自身が守らなくてよい、と対外的にアピールするに等しく、組織防衛でありながら自身の存在意義を否定する劇薬である。
であるとするなら、この司法の腐敗ぶりをどこまで公然化することができるかが、この民法改正運動の帰趨を制すると言ってよい。相変わらず養育費のピンハネや男性の被害者性に対して沈黙しているが、マスコミ報道は「連れ去り」の存在を解禁した。テレビドラマでも「実子誘拐」や子どもを取引材料に使う弁護士たちの悪行が徐々に取り上げられるようになってきた。この傾向は、逆コースに走る裁判所にとっては、おちおちできない事態だろう。高裁弁論期日の「ハチャメチャ家裁祭」に結集を。
自己改革不能な司法官僚システムと家制度
ところで、各国で進められてきた単独親権から共同親権への転換とは、共同親権による父母の共同責任の明示によって、父母の法的な関係と、親子関係を分離することが最終的に目指された。親権制度の改革とはそれを呼ぶ。父母は結婚していようがいまいが父母である。
本国賠訴訟の狙いもそこにある。父母間の不平等の根拠となっているのは、婚姻外の父母の「差別的取り扱い」そのものである。そのことによって婚姻中も含め親の養育権が侵害されるため、父母の共同責任が否定される。よって原告は現行民法と司法のやりたい放題の憲法による規制を求めた。そもそも単独親権に、他方の親の子育てを否定する目的などない。
現在、法制審議会の司法村の住人たちが取りまとめようとしている答申案は、この点を意図的にスキップしている。父母の意見が別れたらわざわざ単独監護者を指定するなど、今と同じ国の過剰介入である。それに対して保守的立場から民間法制審が取りまとめた法案も、結局のところ父母を婚姻による親権者とする点で、婚姻制度に親権制度を従属させている。いくらいい提案をしたところで、大本で対抗案となっていない。現行の婚姻制度は結婚を戸籍、つまり家への所属の問題としているため、戸籍の不合理性を問いかけなければ「差別的取り扱いは合理的」というイデオロギーに取り込まれるのだ。
「部外者」だから合理化される差別的取り扱い
本件一審判決は単独親権制度の立法目的を子どものために「適時適切な意思決定」ができることであると言及している。戦前においては、子も親権のない親(母)も親権者(父)の決定に服する。この場合でも、家に所属する子の処遇を親権者が決めることで、他方親の養育を否定することが目的ではない。しかし、家(戸籍)に所属しない親の場合、「部外者」がその権利性を司法によって正当に尊重されることがあっただろうか。「差別的取り扱いは合理的」とは、「部外者」であるからこそ肯定され、それが家父長制家制度の目的である。
この部外者排除システムの元においては、共同親権は家内部の親に与えられた称号以上の意味はもともとない。国や一審判決の言う「適時適切な意思決定」が単独親権制度の目的なら、共同親権など本来望ましくないからだ。したがって、共同決定ができない場合には、前倒しでその称号がはく奪されて無権利状況に陥る。家制度の番人の司法のもと、個人の尊重と男女同権は敗北を重ねてきた。
戸籍は単なる登録簿ではなくイデオロギーである。イデオロギーでなければ、戸籍に忖度して親権制度の改革を手控える必要は本来ない。そして体制内部の自己改革の道に展望は見いだせない。ぼくたちは、憲法を武器に、控訴審での国の矛盾を引き続きつきながら、彼らのイデオロギーの源泉を白日のもとにさらしていく。「犬神家の一族」のふるさと、諏訪での集会「犬神家の民法改正」もその一手である。(2023.10.29宗像充、共同親権訴訟冒頭コラムから)